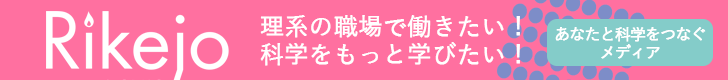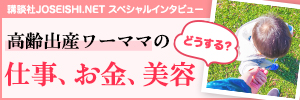- TOP
- > NEWS&TOPICS一覧
- > 【家族のかたち】木村佳乃が直談判してバラエティに出た理由 [FRaU]
【家族のかたち】木村佳乃が直談判してバラエティに出た理由 [FRaU]
2018年04月21日(土) 11時00分配信
最近ますます多様化している、家族のかたちとそこで生まれる悩みの数々。いくつになっても生きていく上で、いろんなときに、いろいろな場面で喜びも悲しみも、苦労も幸せも運んでくる存在。そんな「家族」を考えることで、30代のいまのいろいろを考える「なにか」になれば。
今回は、女優であり2児の母、そして妻である木村佳乃さん。さぞかし目が回るような生活を送っているかと思いきや「手を抜いているので大変ではないです」とサラリと答える。女優という自身の核と親としての責任。2つの異なる道は交差せずとも、ともに歩みを止めず、これまでもこれからも彼女の人生の糧となっている。
今回は、女優であり2児の母、そして妻である木村佳乃さん。さぞかし目が回るような生活を送っているかと思いきや「手を抜いているので大変ではないです」とサラリと答える。女優という自身の核と親としての責任。2つの異なる道は交差せずとも、ともに歩みを止めず、これまでもこれからも彼女の人生の糧となっている。
家族全員で楽しめるものに出たくてバラエティに挑戦したんです
木村さんといえば、最近は、『世界の果てまでイッテQ!』での活躍も話題になった。イモトアヤコさんとタメをはる眉毛を描いたり、熱湯風呂に挑戦したり、ストッキング相撲をしたり、AKB48のダンスに挑戦したり。クールな見た目とはギャップのある「天然」な姿に、視聴者の多くは驚くと同時にお腹の底から大笑いし、大いなる親近感を抱いたと思う。しかも面白いのは、彼女はオファーがあったから出演したのではなく、自らがプロデューサーに「出演させてください」と直談判し挑戦したこと。
「子ども向けのものをやりたいと思ったんです。自分の子どもに観せるためではなく、子ども全体に向けて、家族全員で安心して観られる番組に出させていただきたいなって。それがキッカケなんです。『イッテQ!』は毎週楽しみに観ていましたし、いまも観ています。ただ、番組に出たときは、うちの子どもはまだ小っちゃかったので、あんまりよくわかってなかったみたいですね」
いまはどうですか? お母さんのお仕事はわかっている様子ですか?
「うーん。ハッキリ説明をしていないので、どのくらいわかってるかは不明なんです。働いていることはわかっていると思いますが、具体的には理解していないんじゃないかなと思います。テレビに出ているということだけはわかっているでしょうね。あと、去年、NHK朝の連続テレビ小説『ひよっこ』に出ていたときは、毎日観ていました。ただ、『ひよっこ』っていう仕事だと思っていましたね。劇をしている、というのはわかってると思うんですが、『大人のおままごと』だなっていう感じで。他のお母さんも劇をするものだと思ってるんです。『大人は劇をするものだ』って(笑)」
「子ども向けのものをやりたいと思ったんです。自分の子どもに観せるためではなく、子ども全体に向けて、家族全員で安心して観られる番組に出させていただきたいなって。それがキッカケなんです。『イッテQ!』は毎週楽しみに観ていましたし、いまも観ています。ただ、番組に出たときは、うちの子どもはまだ小っちゃかったので、あんまりよくわかってなかったみたいですね」
いまはどうですか? お母さんのお仕事はわかっている様子ですか?
「うーん。ハッキリ説明をしていないので、どのくらいわかってるかは不明なんです。働いていることはわかっていると思いますが、具体的には理解していないんじゃないかなと思います。テレビに出ているということだけはわかっているでしょうね。あと、去年、NHK朝の連続テレビ小説『ひよっこ』に出ていたときは、毎日観ていました。ただ、『ひよっこ』っていう仕事だと思っていましたね。劇をしている、というのはわかってると思うんですが、『大人のおままごと』だなっていう感じで。他のお母さんも劇をするものだと思ってるんです。『大人は劇をするものだ』って(笑)」
ロンドンで生まれニューヨークも経験。高校生の頃に女優を目指す
ところで、彼女自身はどういった幼少期を過ごしていたのだろう。プロフィールによれば、1976年、イギリスのロンドンで生まれ、中学生の頃にはニューヨーク暮らしも経験。パワフルでポジティブな生き方は、そういったバックグラウンドが影響しているのだろうか。
「どうだろう。ロンドンは3歳までいましたが、あんまり記憶はないですし。とにかく普通の子でした。取り立てて何かに秀でていることもなく。勉強もスポーツも全然ダメだったですし。4月生まれなんで、身長は高かったりしましたが、次女ですから、クラスをまとめるお姉さん的存在でもなく。好きな教科は……国語かな。本が好きだったから。
あと、おばあちゃん子でした、私は。祖母は亡くなるまでずっと一緒に住んでいたんです。よく一緒に相撲を観たのを憶えてますね。マラソン中継とか(笑)」
―では、中学生の頃に経験したニューヨーク暮らしはどうでしたか? カルチャーショックを受けたことは?
「私が過ごしていたころは、あまり治安が良くない時期だったと思います。だから、カルチャーショックだったことといえば、世界には危ない場所があるということを知ったということ。日本って安全なんだなって。
あと、音楽が好きになりました。これは大きなカルチャーショックだったかも。ニューヨークに住んでからヘビーメタルやラップが大好きになったんです。ニューヨークで大流行していましたから。当時、MTVという音楽チャンネルをよく観ていて、それを観てこれは楽しいぞって。CDも日本に比べれば安いですから、たくさん買って。いまも音楽は大好きです。ブルーノ・マーズにハマってますね。レディー・ガガとか。子どもも一緒に聴いて踊ってます(笑)」
「どうだろう。ロンドンは3歳までいましたが、あんまり記憶はないですし。とにかく普通の子でした。取り立てて何かに秀でていることもなく。勉強もスポーツも全然ダメだったですし。4月生まれなんで、身長は高かったりしましたが、次女ですから、クラスをまとめるお姉さん的存在でもなく。好きな教科は……国語かな。本が好きだったから。
あと、おばあちゃん子でした、私は。祖母は亡くなるまでずっと一緒に住んでいたんです。よく一緒に相撲を観たのを憶えてますね。マラソン中継とか(笑)」
―では、中学生の頃に経験したニューヨーク暮らしはどうでしたか? カルチャーショックを受けたことは?
「私が過ごしていたころは、あまり治安が良くない時期だったと思います。だから、カルチャーショックだったことといえば、世界には危ない場所があるということを知ったということ。日本って安全なんだなって。
あと、音楽が好きになりました。これは大きなカルチャーショックだったかも。ニューヨークに住んでからヘビーメタルやラップが大好きになったんです。ニューヨークで大流行していましたから。当時、MTVという音楽チャンネルをよく観ていて、それを観てこれは楽しいぞって。CDも日本に比べれば安いですから、たくさん買って。いまも音楽は大好きです。ブルーノ・マーズにハマってますね。レディー・ガガとか。子どもも一緒に聴いて踊ってます(笑)」
一生、女優でいたい。そう思えることが幸せ
では、女優への憧れを抱くようになったのはいつ頃からでしたか?
「高校生ぐらいからです。昔から物語を読むのが好きでしたし、舞台を観たり、映画を観たりするのが好きだった。
私、夏目漱石がすごく好きで、森田芳光監督も大好きだったので、松田優作さんと藤谷美和子さんが主演の『それから』(’85年)という映画がいまでも忘れられません。それが演じることの原点になっているのかもしれません。こういった世界観が好きだなって」
森田監督とは、その後、映画『失楽園』(’97年)で一緒に仕事をすることとなる。彼女の映画デビュー作でもある。
「森田監督の映画に出る前、『元気をあげる〜救命救急医物語』(’96年)というNHKのドラマで仕事を始めたんですね。いろんな地方出身の人が集まって、年齢もバラバラなところで同じ作品をみんなで毎日つくるというのがすごく楽しくて、できたできないは別として、そこで、このお仕事をもっとやっていきたいなって」
「高校生ぐらいからです。昔から物語を読むのが好きでしたし、舞台を観たり、映画を観たりするのが好きだった。
私、夏目漱石がすごく好きで、森田芳光監督も大好きだったので、松田優作さんと藤谷美和子さんが主演の『それから』(’85年)という映画がいまでも忘れられません。それが演じることの原点になっているのかもしれません。こういった世界観が好きだなって」
森田監督とは、その後、映画『失楽園』(’97年)で一緒に仕事をすることとなる。彼女の映画デビュー作でもある。
「森田監督の映画に出る前、『元気をあげる〜救命救急医物語』(’96年)というNHKのドラマで仕事を始めたんですね。いろんな地方出身の人が集まって、年齢もバラバラなところで同じ作品をみんなで毎日つくるというのがすごく楽しくて、できたできないは別として、そこで、このお仕事をもっとやっていきたいなって」
やりたいことをやりなさい。それが祖母の言いつけでした
それから20年以上が経ち、彼女は日本を代表する女優となった。しかも、美しさをそなえつつエキセントリックな役柄もこなせる希有な役者。気の強い女性だったり、高飛車な女性だったり、教育ママだったり、映画『告白』(’10年)やドラマ『名前をなくした女神』(’11年)で演じたような、いわゆる「嫌な女」だったり。そういった役どころを演じれば、彼女の右に出るものはいないんじゃないかと思うほどハマっている。もちろん、当たり前だけど、本来の彼女はそんな女性とは正反対。
今回の取材を通して感じるのは、木村佳乃という女性は天真爛漫であるということ。『真田丸』で演じた松が限りなく素に近いのではないかなと思う。三谷幸喜氏は役を「当て書き」する作家だというけれど、彼女の本質をよく見抜いていたんだなあとあらためて感心してしまう。
「よく言いますよね、悪い人間を演じるほうがやりがいがあるって。俳優さんのインタビューを読むと。なので、昔から、悪い役への憧れはありました。やってみたいなと常に思っていたと思います」
―でもそうすると、世間の目が気になりませんか? イヤミな女だと思われるんじゃないだろうかとか。
「でもそれは役柄ですから。気にならないです。しかも、視聴者の方々は目が肥えています。昔の女優さんのように、素を全く表に出さないということはなかなか少なくなってきました。良くも悪くも、SNSで何でも拡散されてしまう時代ですから、素はどうしても透けて見えてしまう。だから、作品として魅力的であれば、それでいいかなって。
でも、そういった役を演じることがつらいことももちろんあるんですね。以前、『CO移植コーディネーター』(’11年)というドラマに出たんですが、子どもの臓器移植の話で、私は子どもをネグレクトする母親役を演じたんです。それは精神的にきつかった。非常に意義のある奥深い話でしたけれど、やるほうは大変。
今回の取材を通して感じるのは、木村佳乃という女性は天真爛漫であるということ。『真田丸』で演じた松が限りなく素に近いのではないかなと思う。三谷幸喜氏は役を「当て書き」する作家だというけれど、彼女の本質をよく見抜いていたんだなあとあらためて感心してしまう。
「よく言いますよね、悪い人間を演じるほうがやりがいがあるって。俳優さんのインタビューを読むと。なので、昔から、悪い役への憧れはありました。やってみたいなと常に思っていたと思います」
―でもそうすると、世間の目が気になりませんか? イヤミな女だと思われるんじゃないだろうかとか。
「でもそれは役柄ですから。気にならないです。しかも、視聴者の方々は目が肥えています。昔の女優さんのように、素を全く表に出さないということはなかなか少なくなってきました。良くも悪くも、SNSで何でも拡散されてしまう時代ですから、素はどうしても透けて見えてしまう。だから、作品として魅力的であれば、それでいいかなって。
でも、そういった役を演じることがつらいことももちろんあるんですね。以前、『CO移植コーディネーター』(’11年)というドラマに出たんですが、子どもの臓器移植の話で、私は子どもをネグレクトする母親役を演じたんです。それは精神的にきつかった。非常に意義のある奥深い話でしたけれど、やるほうは大変。
私は役を引きずるほうではないんですが、『告白』のときもそうでしたが気が滅入ってしまって。『告白』は息子に刺される母親の役で、しかもあのとき、息子に刺されるシーンを撮影している最中に体調を崩してしまって……。
あのとき、出演者の間でインフルエンザが大流行したんです。なんだかすごくグッタリして、こういう役は気が重くなるからなあと思っていたら、実はインフルエンザだったっていう(笑)。
ちょうど息子に刺されるシーンの撮影のとき、あまりにもだるくて熱を測ったら39度ぐらいになっていて。撮影を切り上げて途中で帰ることになったんです。助監督さんに『いいご報告をお待ちしております!』と言われて。そのとき、頭がボーッとしていて全然まわってなくて、この人、私が妊娠したと思ってるのかしらってものすごく恥ずかしくなっちゃって、『やだ! なに言ってるんですか!』って。助監督さんは単に、インフルエンザの陰性を願っていただけだったんです(笑)」
―ちなみに、いまはどんな役をやりたいと考えていますか?
「基本的にサスペンスが好きなんですが、デヴィッド・フィンチャー監督の『セブン』(’95年)という映画を久しぶりに観たらすっごく面白くて。20 年以上前の作品ですが、全然古くないんです。こういう映画をやりたいなって」
それは、グウィネス・パルトロウの役をやってみたい、ということですか?
「いえ、ブラッド・ピットの役をやってみたいんです(笑)。若手刑事という歳ではないですけれど。
要するに、素晴らしい映画やドラマって色褪せないんです。いつの時代に観ても面白いし、どの時代でも受け入れられる。それがこの仕事の良さですよね。だからこそ、続ける意義があるというか。
あのとき、出演者の間でインフルエンザが大流行したんです。なんだかすごくグッタリして、こういう役は気が重くなるからなあと思っていたら、実はインフルエンザだったっていう(笑)。
ちょうど息子に刺されるシーンの撮影のとき、あまりにもだるくて熱を測ったら39度ぐらいになっていて。撮影を切り上げて途中で帰ることになったんです。助監督さんに『いいご報告をお待ちしております!』と言われて。そのとき、頭がボーッとしていて全然まわってなくて、この人、私が妊娠したと思ってるのかしらってものすごく恥ずかしくなっちゃって、『やだ! なに言ってるんですか!』って。助監督さんは単に、インフルエンザの陰性を願っていただけだったんです(笑)」
―ちなみに、いまはどんな役をやりたいと考えていますか?
「基本的にサスペンスが好きなんですが、デヴィッド・フィンチャー監督の『セブン』(’95年)という映画を久しぶりに観たらすっごく面白くて。20 年以上前の作品ですが、全然古くないんです。こういう映画をやりたいなって」
それは、グウィネス・パルトロウの役をやってみたい、ということですか?
「いえ、ブラッド・ピットの役をやってみたいんです(笑)。若手刑事という歳ではないですけれど。
要するに、素晴らしい映画やドラマって色褪せないんです。いつの時代に観ても面白いし、どの時代でも受け入れられる。それがこの仕事の良さですよね。だからこそ、続ける意義があるというか。
たとえば、亡くなられた緒形拳さんは私がもっとも尊敬する俳優さんですが、拳さんの出演作には、『鬼畜』(’78年)だったり『楢山節考』(’83年)だったり、素晴らしい作品がたくさんあって、映画の中でイキイキと生きている拳さんを観ると、亡くなった気がしないんです。拳さんは作品の中でずっと生きている。映画を観ればいつでも拳さんに会える。
ですから、素晴らしい職業に就いたなと思うんです。それこそ、誰かに影響を与え、人生を変えてしまうかもしれない作品に出られるというのはすごいこと。私は恵まれた仕事をしているんだなって。
家事や育児と両立するのは大変じゃないというとウソになりますし、不平不満を言い出せばキリがない。でも、それを越える、やりがいのある仕事をさせていただいていると思うと、もっともっと先を見るべきだなって。振り返ってクヨクヨしてはいけないなって」
ですから、素晴らしい職業に就いたなと思うんです。それこそ、誰かに影響を与え、人生を変えてしまうかもしれない作品に出られるというのはすごいこと。私は恵まれた仕事をしているんだなって。
家事や育児と両立するのは大変じゃないというとウソになりますし、不平不満を言い出せばキリがない。でも、それを越える、やりがいのある仕事をさせていただいていると思うと、もっともっと先を見るべきだなって。振り返ってクヨクヨしてはいけないなって」
先を見る」「振り返らない」。なるほど。今回、お話をお伺いしていると、木村さん自身の根っこはそこにあるような気がします。
「後ろを振り返ってもしょうがないと思ってるんです。過ぎちゃったことは過ぎちゃったこと。反省はしますけれど、過ぎたことを後悔してもねって。
実はこれ、一緒に住んでいた祖母によく言われていたことなんです。
『クヨクヨしてはいけないよ。いまはいましかないんだから。いまやりたいことはいまやる。あとであれをやりたかったと後悔するのは時間の無駄。失敗してもいいからやりたいことをやりなさい。死ななきゃ大丈夫だから』って。
明治生まれの祖母はそういう人でした。あの時代の人は強いんです。戦争を体験している人はみんなそうなんだと思います。私自身、忘れっぽいというのもありますけれど、ただやはり、振り返っているヒマがあるなら、いまと明日のことを考える。それに尽きると思いますね」
では、明日以降のことは?
「そこもあんまり考えていても意味がないなって。予定に縛られてしまうと、いまを生きることができなくなる。最初にも言いましたけれど、行き当たりばったりの私ですから(笑)」
明日は明日の風が吹く。Tomorrow is another day. ふと、マーガレット・ミッチェルの小説『風と共に去りぬ』のヒロイン、スカーレット・オハラの名文句を思い出す。映画でもヴィヴィアン・リーが最後に言うセリフだ。彼女の目指す女優とはどういうものか気になった。
「役者業って定年がありませんから、歳を取ったら素敵なおばあちゃんを演じたいとは思いますね。
先日『オリエント急行殺人事件』(’17 年)を観たんですが、ジュディ・デンチってすごいなあと感激しました。80歳を超えているのに、ものすごくカッコいいんです。あんなふうに私も輝き続けられたらいいなって。
『真田丸』でご一緒した草笛光子さんもそうです。草笛さんも84歳になられましたが、誰よりもお元気で、お話をするととっても楽しい。
大竹しのぶさんも大好きでよくお話をします。それこそ、子育てのこととかもいろいろうかがって、勇気づけられますし学ぶこともすごく多いですし。
「後ろを振り返ってもしょうがないと思ってるんです。過ぎちゃったことは過ぎちゃったこと。反省はしますけれど、過ぎたことを後悔してもねって。
実はこれ、一緒に住んでいた祖母によく言われていたことなんです。
『クヨクヨしてはいけないよ。いまはいましかないんだから。いまやりたいことはいまやる。あとであれをやりたかったと後悔するのは時間の無駄。失敗してもいいからやりたいことをやりなさい。死ななきゃ大丈夫だから』って。
明治生まれの祖母はそういう人でした。あの時代の人は強いんです。戦争を体験している人はみんなそうなんだと思います。私自身、忘れっぽいというのもありますけれど、ただやはり、振り返っているヒマがあるなら、いまと明日のことを考える。それに尽きると思いますね」
では、明日以降のことは?
「そこもあんまり考えていても意味がないなって。予定に縛られてしまうと、いまを生きることができなくなる。最初にも言いましたけれど、行き当たりばったりの私ですから(笑)」
明日は明日の風が吹く。Tomorrow is another day. ふと、マーガレット・ミッチェルの小説『風と共に去りぬ』のヒロイン、スカーレット・オハラの名文句を思い出す。映画でもヴィヴィアン・リーが最後に言うセリフだ。彼女の目指す女優とはどういうものか気になった。
「役者業って定年がありませんから、歳を取ったら素敵なおばあちゃんを演じたいとは思いますね。
先日『オリエント急行殺人事件』(’17 年)を観たんですが、ジュディ・デンチってすごいなあと感激しました。80歳を超えているのに、ものすごくカッコいいんです。あんなふうに私も輝き続けられたらいいなって。
『真田丸』でご一緒した草笛光子さんもそうです。草笛さんも84歳になられましたが、誰よりもお元気で、お話をするととっても楽しい。
大竹しのぶさんも大好きでよくお話をします。それこそ、子育てのこととかもいろいろうかがって、勇気づけられますし学ぶこともすごく多いですし。
役者って同じ作品になると、先輩も後輩も子役も意外と対等で、お互いに刺激を受け合う職業なんです。経験を重ねると、頭でっかちになって、凝り固まってきてしまうところもあるので、そういう枠は取り払って、いつでも柔軟な状態でいたいと心がけています」
AIとどう付き合っていくのか。これからの大きな悩みです
振り返らない、クヨクヨしない、予定は立てない、明日は明日の風が吹く。そんな彼女がいまいちばん気になる事柄はどんなことだろう。質問すると「AIですね」と意外な答えが返ってきた。
「AIとどう付き合っていくのか、というのはすごく考えさせられます。家族内の問題として、いま、ホントに悩んでいるというか。いまはなんでもネットで見ることができてしまうじゃないですか。規制できないところにきてしまっている。そうすると、子どもはなんでも調べられるし、見ようと思えばなんでも見られる。何年かすれば、いまよりもっとなんでもできる世の中になってしまう。そんなときに、どうやって子どもたちにAIの使用を規制するのか。これは、子をもつお母さんたちの共通の悩みだと思うんです」
―お子さんたちはAIを使いますか?
「はい。『オッケーグーグル、2+5は?』とか(笑)。いまはそのくらいなので可愛いですけれど。それに子どもたちはYouTubeが大好きです。面白い動画などを自分たちで検索してみていることもあります。私たちが子どもの頃にはなかった、現代の悩みですから、どうすればいいんだろうと途方に暮れることがあります。そういう特集を女性誌でぜひやってほしい。子を育てる親だったらみんな読みたいと思うはずだもの」
ネット社会が子どもに及ぼす影響は計り知れませんよね。
「完全に遮断することは不可能なんです。スマホを持たせないパソコンに触らせない、ということをすれば、仲間はずれにされるとか別の問題が起きてくるでしょうし、あんまり遮断しすぎると、いざそういったものに触れたときに歯止めが利かなくなる可能性もあるんじゃないかなって。もしかすると天才プログラマーになるかもしれないのにそのチャンスを奪ってしまうことになるかもしれない、とかね(笑)。うちの娘たちは、いまはまだリカちゃん人形で遊ぶのが好きですが、この先、どうすればいいのかなというのは、本当に悩みのタネなんです」
「AIとどう付き合っていくのか、というのはすごく考えさせられます。家族内の問題として、いま、ホントに悩んでいるというか。いまはなんでもネットで見ることができてしまうじゃないですか。規制できないところにきてしまっている。そうすると、子どもはなんでも調べられるし、見ようと思えばなんでも見られる。何年かすれば、いまよりもっとなんでもできる世の中になってしまう。そんなときに、どうやって子どもたちにAIの使用を規制するのか。これは、子をもつお母さんたちの共通の悩みだと思うんです」
―お子さんたちはAIを使いますか?
「はい。『オッケーグーグル、2+5は?』とか(笑)。いまはそのくらいなので可愛いですけれど。それに子どもたちはYouTubeが大好きです。面白い動画などを自分たちで検索してみていることもあります。私たちが子どもの頃にはなかった、現代の悩みですから、どうすればいいんだろうと途方に暮れることがあります。そういう特集を女性誌でぜひやってほしい。子を育てる親だったらみんな読みたいと思うはずだもの」
ネット社会が子どもに及ぼす影響は計り知れませんよね。
「完全に遮断することは不可能なんです。スマホを持たせないパソコンに触らせない、ということをすれば、仲間はずれにされるとか別の問題が起きてくるでしょうし、あんまり遮断しすぎると、いざそういったものに触れたときに歯止めが利かなくなる可能性もあるんじゃないかなって。もしかすると天才プログラマーになるかもしれないのにそのチャンスを奪ってしまうことになるかもしれない、とかね(笑)。うちの娘たちは、いまはまだリカちゃん人形で遊ぶのが好きですが、この先、どうすればいいのかなというのは、本当に悩みのタネなんです」
きっと大丈夫。なるようになるから悩まないで
木村さんにとって家族とはどういう存在なのかを最後に聞いてみた。
「責任ということですね。ですから、とにかく、私が健康でいなくてはいけないなって。子どもたちも健康で、事故もなく、楽しく学校へ行ってもらうためにも、私が元気でいなくてはいけないなって。
あと、両親にも元気でいてもらいたい。両親はもう70代。だいぶ体力も落ちてきたので、いたわらなくてはいけませんし。いままで私を支えてくれたので、これからは親を支えるじゃないですが、恩返ししなくちゃいけないなって。私もいい歳ですから、いまから恩返しというのもちょっと遅いんですけれども」
―では、娘さんたちにはどんなふうに育ってほしいと考えていますか?
「女の子なので、人の気持ちを思いやれる愛嬌のある子になってほしいかな。いまはそのくらいしか考えてないなあ。『リトル・マーメイド』のアリエルになりたいって言う子たちですから。ただ、私は若いときから仕事をして楽しかったので、自分のやりたい仕事には就いてほしいなと思っています。できれば、一生続けることのできる、生きがいを感じられる仕事をみつけてほしいなって。
とにかく私は、深く考えず、祖母の言いつけ通り、いまと明日のことを考え生きてきたらこうなった、っていう感じなんです(笑)。だから、娘たちにはもちろん、若い女性たちに言うとするなら、『きっと大丈夫』。私は、悩んでも、夜中にホラー映画を観れば大丈夫になっていたので、深く考え込まなくてもなるようになるんじゃないかなって」
「責任ということですね。ですから、とにかく、私が健康でいなくてはいけないなって。子どもたちも健康で、事故もなく、楽しく学校へ行ってもらうためにも、私が元気でいなくてはいけないなって。
あと、両親にも元気でいてもらいたい。両親はもう70代。だいぶ体力も落ちてきたので、いたわらなくてはいけませんし。いままで私を支えてくれたので、これからは親を支えるじゃないですが、恩返ししなくちゃいけないなって。私もいい歳ですから、いまから恩返しというのもちょっと遅いんですけれども」
―では、娘さんたちにはどんなふうに育ってほしいと考えていますか?
「女の子なので、人の気持ちを思いやれる愛嬌のある子になってほしいかな。いまはそのくらいしか考えてないなあ。『リトル・マーメイド』のアリエルになりたいって言う子たちですから。ただ、私は若いときから仕事をして楽しかったので、自分のやりたい仕事には就いてほしいなと思っています。できれば、一生続けることのできる、生きがいを感じられる仕事をみつけてほしいなって。
とにかく私は、深く考えず、祖母の言いつけ通り、いまと明日のことを考え生きてきたらこうなった、っていう感じなんです(笑)。だから、娘たちにはもちろん、若い女性たちに言うとするなら、『きっと大丈夫』。私は、悩んでも、夜中にホラー映画を観れば大丈夫になっていたので、深く考え込まなくてもなるようになるんじゃないかなって」
※FRaU2018年3月号より一部抜粋
●情報は、FRaU2018年3月号発売時点のものです。