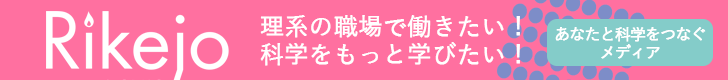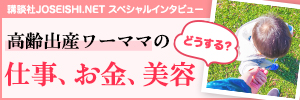- TOP
- > NEWS&TOPICS一覧
- > 芥川賞作家・川上未映子「子どもが生まれて完全に変わった二つのこと」 [FRaU]
芥川賞作家・川上未映子「子どもが生まれて完全に変わった二つのこと」 [FRaU]
2017年06月04日(日) 18時00分配信
作家であり、母であり、妻である川上未映子、39歳。彼女の人生をひもときながら、再婚、出産を選択した理由、母との確執からの卒業、そして、これから残していきたい作品への思いについて聞いた。美しく、ときに可憐に見せながらも、勇ましく戦い続ける彼女の力強い言葉の数々は、青く静かに燃える炎のように、心に響いた。
「写真を撮られるのは苦手なんですよ。いつもは家でパソコンを前にひっそりカタカタやっているのに、日常とのギャップがすごくて(笑)」
そう笑いながらも、カメラの前に立つとくるくると表情を変えてみせる。作家・川上未映子さんは、常に彼女とコミュニケートする人たちの期待に応え、進化し続けてきた人なのではないだろうか。そんな繊細さと、相反する大胆なたくましさが、彼女の言葉や存在から垣間見える。
35歳で経験した初めての妊娠、出産、育児についてあけすけに綴ったエッセイ『きみは赤ちゃん』が、出産や育児を経験した人のみならず、未婚の読者からも多くの共感の声を集め、働く美しき母のロールモデルとなった彼女。そしてこれまで執筆した作品は、芥川賞、谷崎潤一郎賞など名だたる文学賞を受賞。2011年には同じく芥川賞作家の阿部和重さんと再婚するなど、まさに順風満帆、すべてを手に入れてきたかのように思える彼女だが、自身を〝ネガティブ・ネイティブ〞と称するほど根が暗いらしい。
「みなさんあまり言葉にしないだけで、子どもの時期は地獄みたいなものでしょう。とても長い地獄。もちろん一概には言えないけれど、子どもは無力だし、環境を選べないですから。私に限って言えば、子ども時代に笑って過ごしていたという印象は少ないですね。
理由は何重にもあって、一つは父が今でいうマッチョな人だったので、家族みんなが家長である父にとても気を遣っていたこと。母親が家事をすべてやりながら働いていたこともあり、理不尽だなという思いを抱きやすい環境ではありました。同時に、自分も含めていつかみんな死ぬということが私には一大事で。たとえば自分の手を見て、これが焼かれるときが、嘘じゃなく本当に来る、そう気づいたときにすごく怖くなったんです。生きていることや死んでしまうことの意味なんて、普段は見過ごして生きていかざるを得ないことなのに、その根源的な不安がいつも後ろから自分のことを見ているような気がしていました。振り返るとまたいなくなるのだけれど、ふと忘れた頃にノックしてくる。その不安は今もあるし、だから物を書いているのかもしれません」
そう笑いながらも、カメラの前に立つとくるくると表情を変えてみせる。作家・川上未映子さんは、常に彼女とコミュニケートする人たちの期待に応え、進化し続けてきた人なのではないだろうか。そんな繊細さと、相反する大胆なたくましさが、彼女の言葉や存在から垣間見える。
35歳で経験した初めての妊娠、出産、育児についてあけすけに綴ったエッセイ『きみは赤ちゃん』が、出産や育児を経験した人のみならず、未婚の読者からも多くの共感の声を集め、働く美しき母のロールモデルとなった彼女。そしてこれまで執筆した作品は、芥川賞、谷崎潤一郎賞など名だたる文学賞を受賞。2011年には同じく芥川賞作家の阿部和重さんと再婚するなど、まさに順風満帆、すべてを手に入れてきたかのように思える彼女だが、自身を〝ネガティブ・ネイティブ〞と称するほど根が暗いらしい。
「みなさんあまり言葉にしないだけで、子どもの時期は地獄みたいなものでしょう。とても長い地獄。もちろん一概には言えないけれど、子どもは無力だし、環境を選べないですから。私に限って言えば、子ども時代に笑って過ごしていたという印象は少ないですね。
理由は何重にもあって、一つは父が今でいうマッチョな人だったので、家族みんなが家長である父にとても気を遣っていたこと。母親が家事をすべてやりながら働いていたこともあり、理不尽だなという思いを抱きやすい環境ではありました。同時に、自分も含めていつかみんな死ぬということが私には一大事で。たとえば自分の手を見て、これが焼かれるときが、嘘じゃなく本当に来る、そう気づいたときにすごく怖くなったんです。生きていることや死んでしまうことの意味なんて、普段は見過ごして生きていかざるを得ないことなのに、その根源的な不安がいつも後ろから自分のことを見ているような気がしていました。振り返るとまたいなくなるのだけれど、ふと忘れた頃にノックしてくる。その不安は今もあるし、だから物を書いているのかもしれません」
矛盾や疑問が蓄積する日々を 文章で声に出すことを知った
多感とはいえまだ幼かった川上さんには、自分が覚えた矛盾や疑問を伝える手段としての言葉が与えられていなかったという。日に日に不安が膨らんでいくばかりだった彼女が、素直な気持ちを初めて綴ったのが、小学3年生のときに書いた作文だった。矛盾や疑問が蓄積する日々を文章で声に出すことを知った。
「子どもが『なんで私を産んだん? なんで死ぬん?』と言うのはタブー。親に聞いても『子どもは子どもらしく走ってこい!』とあしらわれておしまい(笑)。そんなとき、自由テーマの作文で『みんないつか死んでしまうなら、できれば私は誰よりも先に死にたい』というようなことを書いたんです。そうしたら、先生から名前を呼ばれて、怒られるのかと思いきや拍手をしてくれたんですね。『先生にもその答えはわからないけれど、考え続けることは大事やと思います』と言ってもらえたことがもう嬉しくて。トイレで大泣きしました。初めて他人から認めてもらえたんだなと思いました」
10代で、表向きの教科書には書かれていないことをもっと知りたいという欲求から、図書館へと足繁く通うようになる。そこには、漂白されていない文学という世界が待っていた。
「みんなが悩み苦しんでいること、本当に知りたいことについて触れているのが文学ですよね。でも、読めば読むほど、まったく霧は晴れないわけです。もやもやが言語化されるから更に理屈っぽくなって、がんじがらめになって、あっという間に中二病のできあがり(笑)。でも、物語じゃなくてもっと根源的なことが知りたくなってくる。すると、どうやら哲学というものがあるらしいと。ひらめきや霊感じゃない、誰にとってもロジカルな方法で、感情よりも真理を教えてくれ!というときに読んだのが、カントについての本でした。これだった、私が知りたいのは、という感激がありましたね」
「子どもが『なんで私を産んだん? なんで死ぬん?』と言うのはタブー。親に聞いても『子どもは子どもらしく走ってこい!』とあしらわれておしまい(笑)。そんなとき、自由テーマの作文で『みんないつか死んでしまうなら、できれば私は誰よりも先に死にたい』というようなことを書いたんです。そうしたら、先生から名前を呼ばれて、怒られるのかと思いきや拍手をしてくれたんですね。『先生にもその答えはわからないけれど、考え続けることは大事やと思います』と言ってもらえたことがもう嬉しくて。トイレで大泣きしました。初めて他人から認めてもらえたんだなと思いました」
10代で、表向きの教科書には書かれていないことをもっと知りたいという欲求から、図書館へと足繁く通うようになる。そこには、漂白されていない文学という世界が待っていた。
「みんなが悩み苦しんでいること、本当に知りたいことについて触れているのが文学ですよね。でも、読めば読むほど、まったく霧は晴れないわけです。もやもやが言語化されるから更に理屈っぽくなって、がんじがらめになって、あっという間に中二病のできあがり(笑)。でも、物語じゃなくてもっと根源的なことが知りたくなってくる。すると、どうやら哲学というものがあるらしいと。ひらめきや霊感じゃない、誰にとってもロジカルな方法で、感情よりも真理を教えてくれ!というときに読んだのが、カントについての本でした。これだった、私が知りたいのは、という感激がありましたね」
異性モテとは無縁 活字に恋した思春期
文学と哲学に夢中だった思春期の川上さんは、恋愛経験も少なく、芸能人を好きになる感覚にも一切ピンとこなかった。「音楽が好きで、その作り手としてミュージシャンを尊敬することはあっても、ご本人への興味はまた別ですよね」と。
「いわゆるモテとは無縁なんです。恋愛というものに主体性がなくて……。好きと言われてから一気に恋愛の舞台に上がるという認識の甘さです。ひとりの人とわりに長く付き合う感じでした。高校時代の同級生は、同じように本を読む人で、本を交換して、あっという間に響きあうものがあってという、ほぼ初恋みたいなその相手とずっと一緒にいました。結局のところ、文章とか言葉が好きなんでしょうね。外見よりもどんな言葉を使うかとか、そっちのほうがすごく重要です」
今でこそ乗り越えられたコンプレックスだと言うが、自身の離れ目が嫌でしかたなかったこともあったそう。
「安室奈美恵さんの登場で市民権を得るまで、離れ目はブサイクの象徴だったんです。今はお化粧しているけれど、昔は全然してなかったし。根深く残っているのが、スカートめくり問題。子どものときって、男の子に欲望されることがある種の自信につながるようなことがありますよね。その逆も然りですが、自分を見つめる前に、親から女らしくしろと言われたり、男性から見初められる論理で育つと、男の子からスカートめくりされることが価値になってしまうという辛さがありました。間違っても女の子が『将来は首相になりたい』とかは言えなくて。私はスカートめくりされるような対象じゃなかったけれど、されないことに傷つきもした。傷つく必要なんてまったくないのにね……なんだか腹が立ってきたな(笑)。モテコードから離れて自由に生きている女の人たちにも、そういう理不尽な思いをした歴史はあるんじゃないかな」
「いわゆるモテとは無縁なんです。恋愛というものに主体性がなくて……。好きと言われてから一気に恋愛の舞台に上がるという認識の甘さです。ひとりの人とわりに長く付き合う感じでした。高校時代の同級生は、同じように本を読む人で、本を交換して、あっという間に響きあうものがあってという、ほぼ初恋みたいなその相手とずっと一緒にいました。結局のところ、文章とか言葉が好きなんでしょうね。外見よりもどんな言葉を使うかとか、そっちのほうがすごく重要です」
今でこそ乗り越えられたコンプレックスだと言うが、自身の離れ目が嫌でしかたなかったこともあったそう。
「安室奈美恵さんの登場で市民権を得るまで、離れ目はブサイクの象徴だったんです。今はお化粧しているけれど、昔は全然してなかったし。根深く残っているのが、スカートめくり問題。子どものときって、男の子に欲望されることがある種の自信につながるようなことがありますよね。その逆も然りですが、自分を見つめる前に、親から女らしくしろと言われたり、男性から見初められる論理で育つと、男の子からスカートめくりされることが価値になってしまうという辛さがありました。間違っても女の子が『将来は首相になりたい』とかは言えなくて。私はスカートめくりされるような対象じゃなかったけれど、されないことに傷つきもした。傷つく必要なんてまったくないのにね……なんだか腹が立ってきたな(笑)。モテコードから離れて自由に生きている女の人たちにも、そういう理不尽な思いをした歴史はあるんじゃないかな」
その後、高校のデザイン科へと進学し、かわいい=モテという画一化された価値観ではない社会に触れたことで、表現者としての川上未映子がムクムクと行動を始めた。
「軍払い下げの鉄板入りの靴を履いたり、金髪では物足りずオレンジ色の髪にしたり、いかに目立つか、より面白いか、そのほうがモテることより断然、価値があった。そういう文化の中で過ごせたことは幸運でしたね。その頃は、哲学の勉強をしたいとも考えていたし、歌を歌いたくてバンドをやったりもしました。でも、夢を追いかけるだけでは成り立たない家庭環境だったので、すぐ働き出しましたけど」
当時、弟を大学へ行かせるため、書店員や歯科助手、高級クラブのホステスをするなど昼夜問わず働いていた彼女は、通信制大学の存在を知り、それなら自分でもやりくりできると心を躍らせたそう。「キャンパスライフなんてどうでもいい。とにかく学びたい」の一心で勉学に励んだ。
「軍払い下げの鉄板入りの靴を履いたり、金髪では物足りずオレンジ色の髪にしたり、いかに目立つか、より面白いか、そのほうがモテることより断然、価値があった。そういう文化の中で過ごせたことは幸運でしたね。その頃は、哲学の勉強をしたいとも考えていたし、歌を歌いたくてバンドをやったりもしました。でも、夢を追いかけるだけでは成り立たない家庭環境だったので、すぐ働き出しましたけど」
当時、弟を大学へ行かせるため、書店員や歯科助手、高級クラブのホステスをするなど昼夜問わず働いていた彼女は、通信制大学の存在を知り、それなら自分でもやりくりできると心を躍らせたそう。「キャンパスライフなんてどうでもいい。とにかく学びたい」の一心で勉学に励んだ。
小説を書き始めたのは、 若いとは決していえない30歳のとき。
学生時代から行っていた音楽活動が実を結び、26歳で歌手デビュー、29歳のときには『ユリイカ 11月号 特集*文化系女子カタログ』(青土社)にて、詩「先端で、さすわ さされるわ そらええわ」でテキストデビューを果たす。その後発表された同名詩集にて、中原中也賞を受賞することとなった。そして、小説を書き始めたのは、若いとは決していえない30歳のときのこと。
「若い頃は……、と振り返るのはやっぱり20代の自分のことですよね。私にとって、30歳は小説を書き始めたという転換期でもありましたし、若さと老いの境だったとも思う。個人差はあるだろうけど、私はカウントダウン症候群なところがあるので、25歳の時点で、『ああ、老いが始まったな』と、しみじみ思ったのをよく覚えています。今思うと早いですよね(笑)。余談ですが、私の男性の友だちが毛髪活性の薬を飲んでいて、『ハゲるのは自然なことやんか』と言ったら、『努力もせんとハゲんな』と返してきたんです。なんだか、それに妙に感心して(笑)。私も定期的に皮膚科へ通うとかサプリを飲むとか、生活を見直すことはやってもいいかなと思えた。アンチエイジング、全然いいじゃないですか。みんなその人それぞれの優先順位があるし、好きなようにしたらいいんです」
「若い頃は……、と振り返るのはやっぱり20代の自分のことですよね。私にとって、30歳は小説を書き始めたという転換期でもありましたし、若さと老いの境だったとも思う。個人差はあるだろうけど、私はカウントダウン症候群なところがあるので、25歳の時点で、『ああ、老いが始まったな』と、しみじみ思ったのをよく覚えています。今思うと早いですよね(笑)。余談ですが、私の男性の友だちが毛髪活性の薬を飲んでいて、『ハゲるのは自然なことやんか』と言ったら、『努力もせんとハゲんな』と返してきたんです。なんだか、それに妙に感心して(笑)。私も定期的に皮膚科へ通うとかサプリを飲むとか、生活を見直すことはやってもいいかなと思えた。アンチエイジング、全然いいじゃないですか。みんなその人それぞれの優先順位があるし、好きなようにしたらいいんです」
根負けで入籍 35歳からの妊活と出産
もともと結婚にあまり前向きではなかったという川上さんが、作家の阿部和重さんとの入籍を決意したのは、なんと彼女の根負けだったとか。
「戸籍制度を設けているのは日本と台湾くらい。まったくの時代遅れで、廃止になればいいと思っています。なので入籍には相当な時間をかけて話し合いましたが、相手がどうしても入籍したいという考えだったので、平行線のままでもしょうがないと、私が折れることになりました。先日のベッキーさんの報道のときも――その問題自体にまったく興味はないけれど、でもたとえばゲスの極み乙女。の彼がもし結婚していなかったら、こんな騒ぎにならなかったかと思うと複雑な気分になりますよね。未婚者の二股、三股、というのであれば、ここまでの制裁は下されないでしょう。結婚という契約のお墨付きの強さをあらためて思い知らされました」
『ザ・フェミニズム』(筑摩書房)の中で、上野千鶴子さんは結婚を「自分の身体の性的使用権を生涯にわたって特定の異性に対して排他的に譲渡する契約」と定義した。川上さん自身も、「結婚は身体だけの問題ではないけれど、でもそのとおり。私にとっても難しいもの」と断言する。
「本来自由な人間の在り方に、無理矢理線を引く制度ですからね。結婚には良い面もありますが、でもある面では思考停止の状態でもあるわけです。人間は変わっていくものだからこそ、私はいろんな家族の形態があっていいと思うんです。シングルマザーも堂々と増えていけば、多様性が受容されていく。自分が制度や社会を変えるんだとは思えなくても、自分の選んだことに自信を持ちたい。結婚も離婚も、子どもを持つも持たないもそう。性格も育った環境もみんな違うのだから、できることなら既存の価値観に合わせずに、自信を持って自分がより良く生きるための選択をする。でも難しいんですよね。古い価値観ってどうしようもなくすり込まれてるから。それをひとつひとつ確認して取り除いていくのは、本当に大変な作業」
「戸籍制度を設けているのは日本と台湾くらい。まったくの時代遅れで、廃止になればいいと思っています。なので入籍には相当な時間をかけて話し合いましたが、相手がどうしても入籍したいという考えだったので、平行線のままでもしょうがないと、私が折れることになりました。先日のベッキーさんの報道のときも――その問題自体にまったく興味はないけれど、でもたとえばゲスの極み乙女。の彼がもし結婚していなかったら、こんな騒ぎにならなかったかと思うと複雑な気分になりますよね。未婚者の二股、三股、というのであれば、ここまでの制裁は下されないでしょう。結婚という契約のお墨付きの強さをあらためて思い知らされました」
『ザ・フェミニズム』(筑摩書房)の中で、上野千鶴子さんは結婚を「自分の身体の性的使用権を生涯にわたって特定の異性に対して排他的に譲渡する契約」と定義した。川上さん自身も、「結婚は身体だけの問題ではないけれど、でもそのとおり。私にとっても難しいもの」と断言する。
「本来自由な人間の在り方に、無理矢理線を引く制度ですからね。結婚には良い面もありますが、でもある面では思考停止の状態でもあるわけです。人間は変わっていくものだからこそ、私はいろんな家族の形態があっていいと思うんです。シングルマザーも堂々と増えていけば、多様性が受容されていく。自分が制度や社会を変えるんだとは思えなくても、自分の選んだことに自信を持ちたい。結婚も離婚も、子どもを持つも持たないもそう。性格も育った環境もみんな違うのだから、できることなら既存の価値観に合わせずに、自信を持って自分がより良く生きるための選択をする。でも難しいんですよね。古い価値観ってどうしようもなくすり込まれてるから。それをひとつひとつ確認して取り除いていくのは、本当に大変な作業」
子どもが生まれたことで、 完全に変わったことが二つある。
そんな恋愛脳ではない彼女だが、阿部和重さんとの恋愛の最中に「子どもが欲しい」と言われたことをきっかけに、「子どもを持ちたいと考えたことがなかった」という内面に変化が訪れる。35歳という自身の年齢のことも考え、妊活を開始し、ほどなくして妊娠。今でもその選択に後悔はないが、「ここまで大変だとは思っていなかった」とも。
「妊娠は自分の身体が変化していくから、これはこれでしんどかったけれど、出てきたらもうすごかったよね。命を預かることの大変さも、自分の時間がなくなることも、眠れないという辛さも、想像以上でした。でも、始まっちゃったらやるしかない。育児も仕事も自転車操業です(笑)」
子どもが生まれたことで、完全に変わったことが二つある。一つは、自身の母親との関係だ。
「複雑な家庭環境だったので、自分が母を守らなければならないと思い込んでいて、だから、自分が生まれてくる子どもにしてあげられることがあるなら、全部母にしてあげたいと考えていたんですね。でも、子どもを産んでみたら、母親というのは子どもが元気で笑っていればそれでいいんだということを実感できた。だから、私は母のことをもう心配しなくていい、と初めて思えた。子どもを産んで親になって初めて、私も母の子どもになれたんです。共依存関係が、健全に切れましたね」
二つ目の変化が、夫婦関係が180度変わったこと。
『きみは赤ちゃん』で出産を経た夫婦について彼女はこう記している。「出産を経験した夫婦とは、もともと他人であったふたりが、かけがえのない唯一の他者を迎え入れて、さらに完全な他人になっていく、その過程である」と。まさに、ファンタジーなき経験者の声である。
「家族になっていく過程と表現する人もいるかもしれないけれど、私の場合は違って、完全なる他人になっていきました。恋愛中って頭がふわっとしているし、お互い余裕があるから優しくできる。結婚していてもしばらくは恋人同士のままなんですよね。本当に地が出るのは生まれてから。子どもができると、夫婦はもう一度出会い直すことになる。お互いに、もう同じ人と思ってはいけない。自分も必死だし、相手のことが客観的に見えるようになるので。だから、これから結婚を考えている方は、まず相手を好きなことは大前提として、理想の結婚相手がそのまま最良の父親になる、という考え方は、ちょっと見直してもいいのかも……」
「妊娠は自分の身体が変化していくから、これはこれでしんどかったけれど、出てきたらもうすごかったよね。命を預かることの大変さも、自分の時間がなくなることも、眠れないという辛さも、想像以上でした。でも、始まっちゃったらやるしかない。育児も仕事も自転車操業です(笑)」
子どもが生まれたことで、完全に変わったことが二つある。一つは、自身の母親との関係だ。
「複雑な家庭環境だったので、自分が母を守らなければならないと思い込んでいて、だから、自分が生まれてくる子どもにしてあげられることがあるなら、全部母にしてあげたいと考えていたんですね。でも、子どもを産んでみたら、母親というのは子どもが元気で笑っていればそれでいいんだということを実感できた。だから、私は母のことをもう心配しなくていい、と初めて思えた。子どもを産んで親になって初めて、私も母の子どもになれたんです。共依存関係が、健全に切れましたね」
二つ目の変化が、夫婦関係が180度変わったこと。
『きみは赤ちゃん』で出産を経た夫婦について彼女はこう記している。「出産を経験した夫婦とは、もともと他人であったふたりが、かけがえのない唯一の他者を迎え入れて、さらに完全な他人になっていく、その過程である」と。まさに、ファンタジーなき経験者の声である。
「家族になっていく過程と表現する人もいるかもしれないけれど、私の場合は違って、完全なる他人になっていきました。恋愛中って頭がふわっとしているし、お互い余裕があるから優しくできる。結婚していてもしばらくは恋人同士のままなんですよね。本当に地が出るのは生まれてから。子どもができると、夫婦はもう一度出会い直すことになる。お互いに、もう同じ人と思ってはいけない。自分も必死だし、相手のことが客観的に見えるようになるので。だから、これから結婚を考えている方は、まず相手を好きなことは大前提として、理想の結婚相手がそのまま最良の父親になる、という考え方は、ちょっと見直してもいいのかも……」
赤ちゃんが生まれてから もう一度出会い直すのが夫婦
かつて主婦の友だちから聞いた「一緒に戦う仲間だったはずの夫が、産んだ瞬間、最初に倒す敵になる」という言葉に共感することもあった。
「これ聞いたとき思わず笑っちゃったんだけど、でも、リアリティありすぎて笑えないよね(笑)。女は、母は、こうじゃないといけないというすり込みがあるし、男には男だからしなくてもいい、というすり込みがある。だから、男と女が生活するということは基本的に難しいんですよ。『結婚は墓場だ』っていうのは、家庭を顧みない奔放な男性の側の論理だと思っていたけど、『同じ墓場でも、そっちはまだ昼間の明るい墓場でしょ。こっちはひたすら寝れないという、暗くて恐ろしい真夜中の墓場だよ』って言いたくなった(笑)」
女性から言えば本音、男性から見ると少々厳しくも思える言葉を連発しながらも、「自分が極端にパートナーに対してフェアネスを求めていることは自負している」のだそう。産んでみてからわかったことも、たくさんあったという。この4年間は、共に働いていくためにお互いのスタイルや考えをすり合わせ、二人でアジャストしていく日々だった。
「私がこういうことを言うから、あべちゃん(阿部和重さんのこと)は家事をしないのではと思われてしまうけど、違うんです。夫はフィンランドで通用するくらいの高いレベル(※)。それでもやっぱり、子育てが入ってくると、男女で完璧にフェアになることはないんですよね」 (※男女同権が浸透しており、経済的に自立した女性も多く、一般的に結婚生活における主導権は妻にあるとも言われている)
コミュニケーションを取る努力をしても、子どもを産んで働きながら、お互いに不満を溜め込まない状態でいられるのは、奇跡的なことなのだ。
「もし結婚して、共働きで相手と一緒に子どもを育てたいと思うなら、家事ができる人、料理ができる人、頭の柔らかい人かどうかが、本当に重要になってきます。話を聞いてくれて、意見も言ってくれて、生活を変えていけるだけの器がある人。好きで信頼できる相手であることを前提に、そういう意味では恋愛と子どもを持つことはやっぱり別だと言いたい。女性も男性も、30歳を過ぎて後から学べることには限りがあるし、アジャストが難しい。男女は相性なので、いつでも婚姻関係を見直すことができるよう、自分の心に正直でいられるよう、職業を持っておいたほうがいいとも思います。働きながら子どもを育てるのは誰もができることではないし、できるから偉いわけじゃない。一生をかけて仕事をまっとうしたい人は子どもを持たなくてもいいし、両方できる人がいてもいい。結局は自分をよく知ることが大事なんだと思います」
阿部さんほど理解のある旦那さんでもアジャストすることが難しいのだとしたら、夫婦円満の秘訣なんて存在するのだろうか。
「うーん、秘訣はないと思う。生きてることは、常にトライ&エラーだから。専業主婦と稼ぎ頭の夫でうまくまわっているところだってあるし、全てはケースバイケースなんですよね。でも、私たちの場合は常に試行錯誤だから、仲は良いけど衝突することは多いです。常にお互いに仕事をする時間の奪い合いなので、まさに映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』みたいな感じ。『どこに行けば時間があるんだー!』って(笑)。夫も私が相手じゃなかったらスルーされていたかもしれないところも、きちんと話しあう。でも、私も夫に『男なんだから』みたいな要求を一切しないし、これまで男女がそれぞれ何となく課せられてきたことを言語化して捉え直す必要な作業なんですよね」
「これ聞いたとき思わず笑っちゃったんだけど、でも、リアリティありすぎて笑えないよね(笑)。女は、母は、こうじゃないといけないというすり込みがあるし、男には男だからしなくてもいい、というすり込みがある。だから、男と女が生活するということは基本的に難しいんですよ。『結婚は墓場だ』っていうのは、家庭を顧みない奔放な男性の側の論理だと思っていたけど、『同じ墓場でも、そっちはまだ昼間の明るい墓場でしょ。こっちはひたすら寝れないという、暗くて恐ろしい真夜中の墓場だよ』って言いたくなった(笑)」
女性から言えば本音、男性から見ると少々厳しくも思える言葉を連発しながらも、「自分が極端にパートナーに対してフェアネスを求めていることは自負している」のだそう。産んでみてからわかったことも、たくさんあったという。この4年間は、共に働いていくためにお互いのスタイルや考えをすり合わせ、二人でアジャストしていく日々だった。
「私がこういうことを言うから、あべちゃん(阿部和重さんのこと)は家事をしないのではと思われてしまうけど、違うんです。夫はフィンランドで通用するくらいの高いレベル(※)。それでもやっぱり、子育てが入ってくると、男女で完璧にフェアになることはないんですよね」 (※男女同権が浸透しており、経済的に自立した女性も多く、一般的に結婚生活における主導権は妻にあるとも言われている)
コミュニケーションを取る努力をしても、子どもを産んで働きながら、お互いに不満を溜め込まない状態でいられるのは、奇跡的なことなのだ。
「もし結婚して、共働きで相手と一緒に子どもを育てたいと思うなら、家事ができる人、料理ができる人、頭の柔らかい人かどうかが、本当に重要になってきます。話を聞いてくれて、意見も言ってくれて、生活を変えていけるだけの器がある人。好きで信頼できる相手であることを前提に、そういう意味では恋愛と子どもを持つことはやっぱり別だと言いたい。女性も男性も、30歳を過ぎて後から学べることには限りがあるし、アジャストが難しい。男女は相性なので、いつでも婚姻関係を見直すことができるよう、自分の心に正直でいられるよう、職業を持っておいたほうがいいとも思います。働きながら子どもを育てるのは誰もができることではないし、できるから偉いわけじゃない。一生をかけて仕事をまっとうしたい人は子どもを持たなくてもいいし、両方できる人がいてもいい。結局は自分をよく知ることが大事なんだと思います」
阿部さんほど理解のある旦那さんでもアジャストすることが難しいのだとしたら、夫婦円満の秘訣なんて存在するのだろうか。
「うーん、秘訣はないと思う。生きてることは、常にトライ&エラーだから。専業主婦と稼ぎ頭の夫でうまくまわっているところだってあるし、全てはケースバイケースなんですよね。でも、私たちの場合は常に試行錯誤だから、仲は良いけど衝突することは多いです。常にお互いに仕事をする時間の奪い合いなので、まさに映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』みたいな感じ。『どこに行けば時間があるんだー!』って(笑)。夫も私が相手じゃなかったらスルーされていたかもしれないところも、きちんと話しあう。でも、私も夫に『男なんだから』みたいな要求を一切しないし、これまで男女がそれぞれ何となく課せられてきたことを言語化して捉え直す必要な作業なんですよね」
PROFILE
川上未映子 mieko kawakami
1979年、大阪府生まれ。2007年、初めての中編小説『わたくし率 イン 歯ー、または世界』が第137回芥川賞候補となる。同年、早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞を受賞。’08年、『乳と卵』が第138回芥川賞を受賞。 ’09年、長編小説『ヘヴン』を発表し、芸術選奨文部科学大臣新人賞、紫式部文学賞を受賞。’12年に男児を出産した。最新刊は『おめかしの引力』(朝日新聞出版)。
1979年、大阪府生まれ。2007年、初めての中編小説『わたくし率 イン 歯ー、または世界』が第137回芥川賞候補となる。同年、早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞を受賞。’08年、『乳と卵』が第138回芥川賞を受賞。 ’09年、長編小説『ヘヴン』を発表し、芸術選奨文部科学大臣新人賞、紫式部文学賞を受賞。’12年に男児を出産した。最新刊は『おめかしの引力』(朝日新聞出版)。