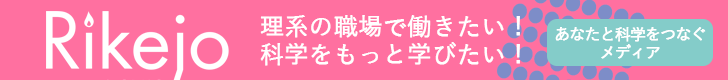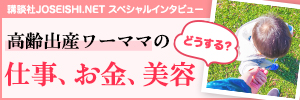- TOP
- > NEWS&TOPICS一覧
- > 『家族という病』の著者・下重暁子さん「期待するなら家族ではなく自分に」[mi-mollet]
『家族という病』の著者・下重暁子さん「期待するなら家族ではなく自分に」[mi-mollet]
2018年09月07日(金) 19時10分配信
「分かち合えない」「わかり合えない」、だから男と女は面白い——。そんな夫婦観を綴って話題となっている下重暁子さんの新刊『夫婦という他人』。「自分で自分を食べさせていく」と心に決め、それを達成するために歩んでこられた下重さん。今回は、読者の抱える夫婦、家族の悩みから、下重さんの考え方をいろいろと伺いました。気持ちがラクになる視点がいっぱいですので、ぜひご一読ください!
自分に期待して生きることは想像以上に嬉しい
「自分のことは自分で食べさせていく」。幼い頃にそう決心し、82歳の現在まで、何度も壁にぶつかりながらもその信念を貫き続けてきた下重暁子さん。36歳のときに3歳年下の男性と結婚をしますが、その後も財布は別々の完全独立採算制で生活。仕事を続けるのはもちろん、家事もそれぞれがおこなう。夫のことを“つれあい”と呼び、「お互いに“個”の存在なのだからなかなか理解できないところもあって当たり前」という夫婦観で向き合ってきたそうです。
mi-mollet編集部には、「夫が何も手伝ってくれない。自分中心な夫に嫌気がさし、離婚を考えている」、「子供ができて以来、女として見てもらえないのがつらい」といった声が多く寄せられていますが、下重さんはそういった悩みをどのように受け止められるのでしょう?
「よく『夫が結婚記念日を忘れていた』という嘆きを耳にしますが、皆さん、夫にとても期待しているのだなと感じます。でも忘れたもんはどうしようもない。そこに期待してガッカリする時間のほうがもったいないと、私などは思ってしまいますね。
夫婦といっても、最初から“個”としても違えば、育った環境も違います。ですから気持ちが通じないなんて当たり前。それよりも私は、自分に対しても家族に対しても、もっと“個”を大事にすべきだと思っているのですよ。結局、人は一人で生まれて一人で死んでいくもの。その覚悟を持てば、自分らしく生きていけるものです。私は幼くしてその喜びを知りましたから、つれあいにまったく期待していませんし、自分にも期待してほしくないと思っています。ただしその分、経済的、精神的自立は貫いてきました。結婚してからずっと独立採算制をとってきたことも誇りに思っています。
要するに、私は夫にではなく自分に期待して生きてきたんですね。皆さんも、期待するなら自分にしましょうよ。自分になら、どれだけ過剰な期待をしてもかまわないんですから。もちろん努力もいりますよ。期待にこたえられなかったら、それは全部自分のせい。誰のせいにもできませんから。しんどいことですが、自分の脚で立っているという喜びは想像以上に大きいものでもありますよ」
mi-mollet編集部には、「夫が何も手伝ってくれない。自分中心な夫に嫌気がさし、離婚を考えている」、「子供ができて以来、女として見てもらえないのがつらい」といった声が多く寄せられていますが、下重さんはそういった悩みをどのように受け止められるのでしょう?
「よく『夫が結婚記念日を忘れていた』という嘆きを耳にしますが、皆さん、夫にとても期待しているのだなと感じます。でも忘れたもんはどうしようもない。そこに期待してガッカリする時間のほうがもったいないと、私などは思ってしまいますね。
夫婦といっても、最初から“個”としても違えば、育った環境も違います。ですから気持ちが通じないなんて当たり前。それよりも私は、自分に対しても家族に対しても、もっと“個”を大事にすべきだと思っているのですよ。結局、人は一人で生まれて一人で死んでいくもの。その覚悟を持てば、自分らしく生きていけるものです。私は幼くしてその喜びを知りましたから、つれあいにまったく期待していませんし、自分にも期待してほしくないと思っています。ただしその分、経済的、精神的自立は貫いてきました。結婚してからずっと独立採算制をとってきたことも誇りに思っています。
要するに、私は夫にではなく自分に期待して生きてきたんですね。皆さんも、期待するなら自分にしましょうよ。自分になら、どれだけ過剰な期待をしてもかまわないんですから。もちろん努力もいりますよ。期待にこたえられなかったら、それは全部自分のせい。誰のせいにもできませんから。しんどいことですが、自分の脚で立っているという喜びは想像以上に大きいものでもありますよ」
情に流されてはダメ。心を鬼にして離れて。
続いて、「育児熱心な夫と完璧主義で頑固な実母が険悪な仲に。間に立たされ疲れ果て、実家を出ることで夫婦の意見は一致。でも、いろいろ迷って決断できない」というお悩みについても相談させていただきました。母親との関係に悩む読者は少ないようですが、実は下重さんもかつて同じ経験をしたことがあるそう。
「私は母親から異常に愛されていたんですね。結婚したとき、つれあいが私と母の暮らす家に転がり込んできたものですから、母は私を取られたと思ったのでしょう。それとなく、つれあいの事をよく言わない。私はそんな母親を見るのが嫌で、距離を置くしかないと決心しました。それで家を出たんです。一人になったことで必然的に母も、私たちとの関係の結び方について冷静に考えるようになったのでしょう。だんだんつれあいの愚痴も言わなくなりました。
やはり近くにいすぎると、人はどうしても期待したり依存したりしやすくなってしまうのでしょうね。母を置いて出るのは辛いものがありましが、情に流されてはお互いのためにならない。そう思って、心を鬼にして距離を取ったのです。ただいきなりすべて断ち切るのではなく、家を出た後も毎晩電話だけはかけていました。母はそれを楽しみにしてくれていたようですが、これは本当のところ、母のためというより自分が安心するためでもありましたね」
では反対に、夫から別れたいと切り出された場合はどうしたらいいのでしょう? アラフォー世代になると、「長年連れ添った夫からある日突然『一人になりたい』と言われた」といった悩みも寄せられていますが、こういった場合もやはり距離をとることが賢明なのでしょうか?
「夫婦なんていつ別れるか分からないもの。人の愛なんてはかないものだし、それは自分も同じです。そのときどうするか……。私は、大事なのは自分で決めることだと思っています。相手が別れたいと言っても、別れたくないとなるような方法を見つけるなり、相手のタイミングではなく自分のタイミングで別れを決心するなり……。決断を相手が下してしまうと、ずっとモヤモヤして愚痴を言い続ける人生になってしまいますから」
「私は母親から異常に愛されていたんですね。結婚したとき、つれあいが私と母の暮らす家に転がり込んできたものですから、母は私を取られたと思ったのでしょう。それとなく、つれあいの事をよく言わない。私はそんな母親を見るのが嫌で、距離を置くしかないと決心しました。それで家を出たんです。一人になったことで必然的に母も、私たちとの関係の結び方について冷静に考えるようになったのでしょう。だんだんつれあいの愚痴も言わなくなりました。
やはり近くにいすぎると、人はどうしても期待したり依存したりしやすくなってしまうのでしょうね。母を置いて出るのは辛いものがありましが、情に流されてはお互いのためにならない。そう思って、心を鬼にして距離を取ったのです。ただいきなりすべて断ち切るのではなく、家を出た後も毎晩電話だけはかけていました。母はそれを楽しみにしてくれていたようですが、これは本当のところ、母のためというより自分が安心するためでもありましたね」
では反対に、夫から別れたいと切り出された場合はどうしたらいいのでしょう? アラフォー世代になると、「長年連れ添った夫からある日突然『一人になりたい』と言われた」といった悩みも寄せられていますが、こういった場合もやはり距離をとることが賢明なのでしょうか?
「夫婦なんていつ別れるか分からないもの。人の愛なんてはかないものだし、それは自分も同じです。そのときどうするか……。私は、大事なのは自分で決めることだと思っています。相手が別れたいと言っても、別れたくないとなるような方法を見つけるなり、相手のタイミングではなく自分のタイミングで別れを決心するなり……。決断を相手が下してしまうと、ずっとモヤモヤして愚痴を言い続ける人生になってしまいますから」
親の“個”としての人生を知れるのが介護
もう一つ、アラフォー世代になると増えるのが介護に関する悩み。編集部にも「母が認知症に。家族が介護することができないので施設に入れたのですが、後ろめたさでいっぱいです」、「父が要介護状態ですが、母は介護サポートも受けずに孤立気味。私が母にしてあげられることは何なのでしょう」といった様々な声が寄せられています。下重さんも義理の母親の介護をされた経験をお持ちですが、「介護は難しい」と振り返ります。
「親たちを看取って、死にも“個”があると幸せだな、と感じたものです。“個”があるというのは、つまり親を分かってあげるということ。でもこれが一番難しい。私の友人に介護の専門家がいるのですが、親の介護をしたとき『アナタは私のことが何も分かってないわね』と言われたそうです。友人は、親は年だからとあっさりした食べ物ばかり作っていたのですが、本当は肉やうなぎが大好物だったそう。そんなふうに、親のことって意外と知らないもの。それを一番知るときが、介護のときでもあると思うんです。親は何を好きで何が嫌いでどんなことを考えているのか……。親ってなかなか自分のことを子供には話しませんからね。私は母の死後、母が書いて父に送った100通の手紙を見つけたんです。そこには『どうしても女の子を産みたい』という思いが切々と綴られていて、私は母がどんな思いで私を産んだのか初めて思い知ったものです。
介護は、そんな親の語らぬ思いを知れる良い時期。介護施設は、物理的なケアはしてくれても心のケアには限界があります。だからこそ家族がその人の歴史を聞く。どんな人にも“個”の人生がありますから、尊敬の念を持って聞かせていただくことが大事で、決して“親”という役割で見ないでほしいと思うのです」
「親たちを看取って、死にも“個”があると幸せだな、と感じたものです。“個”があるというのは、つまり親を分かってあげるということ。でもこれが一番難しい。私の友人に介護の専門家がいるのですが、親の介護をしたとき『アナタは私のことが何も分かってないわね』と言われたそうです。友人は、親は年だからとあっさりした食べ物ばかり作っていたのですが、本当は肉やうなぎが大好物だったそう。そんなふうに、親のことって意外と知らないもの。それを一番知るときが、介護のときでもあると思うんです。親は何を好きで何が嫌いでどんなことを考えているのか……。親ってなかなか自分のことを子供には話しませんからね。私は母の死後、母が書いて父に送った100通の手紙を見つけたんです。そこには『どうしても女の子を産みたい』という思いが切々と綴られていて、私は母がどんな思いで私を産んだのか初めて思い知ったものです。
介護は、そんな親の語らぬ思いを知れる良い時期。介護施設は、物理的なケアはしてくれても心のケアには限界があります。だからこそ家族がその人の歴史を聞く。どんな人にも“個”の人生がありますから、尊敬の念を持って聞かせていただくことが大事で、決して“親”という役割で見ないでほしいと思うのです」
下重暁子という人間は存在しないのがとても不快
自分も、家族も、友人も、すべての人を“個”として認め向き合ってきた下重さん。その生き方は一見孤独で寂しいもののように思えるかもしれませんが、そうして82年間生きてきて、「孤独ほど贅沢で愉快なものはない」という境地にたどり着かれたそう。そんな下重さんが、唯一“個”の人生として成し得ていないとボヤいていることが……。それは、名前。
「私は結婚して姓が変わっていますから、戸籍上は下重暁子という人間はどこにもいないんですよ。それがとっても不快。結局それって、“個”の名前ではなくて“家”の名前ですからね。今も日本は夫婦別姓が認められていませんから、あちこちで裁判をやっていますけど、遅々として進まない。自分の名前で死ぬためには、もはやペーパー離婚もやむを得ないかもしれない、と思っているほどなのです」
「私は結婚して姓が変わっていますから、戸籍上は下重暁子という人間はどこにもいないんですよ。それがとっても不快。結局それって、“個”の名前ではなくて“家”の名前ですからね。今も日本は夫婦別姓が認められていませんから、あちこちで裁判をやっていますけど、遅々として進まない。自分の名前で死ぬためには、もはやペーパー離婚もやむを得ないかもしれない、と思っているほどなのです」
『夫婦という他人』
結婚しているからこそ、つい相手に寄りかかって甘えてしまう。そんな結婚のワナに陥らず、経済的にも精神的にも自立して生きてきた著者の夫婦観を語った最新刊。「独立採算制の結婚もあっていい」、「子はかすがいのウソ」、「夫婦は二人で一対ではない」など、考えさせられる視点がたくさん。二人でいるのに孤独、と感じている方にはぜひ読んでもらいたい1冊です。
下重 暁子
1936年生まれ。早稲田大学を卒業後、アナウンサーとしてNHKに入局。1968年にフリーとなり、民放キャスターを経た後、文筆活動に入る。『家族という病』(幻冬舎新書)、『鋼の女―最後の瞽女・小林ハル』(集英社文庫)など著書多数。最新著書『夫婦という他人』(講談社+α新書)、『極上の孤独』(幻冬舎新書)が話題となっている。
下重 暁子
1936年生まれ。早稲田大学を卒業後、アナウンサーとしてNHKに入局。1968年にフリーとなり、民放キャスターを経た後、文筆活動に入る。『家族という病』(幻冬舎新書)、『鋼の女―最後の瞽女・小林ハル』(集英社文庫)など著書多数。最新著書『夫婦という他人』(講談社+α新書)、『極上の孤独』(幻冬舎新書)が話題となっている。