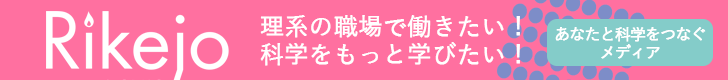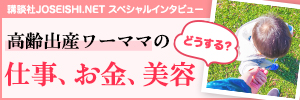- TOP
- > NEWS&TOPICS一覧
- > 『寝ても覚めても』原作者、「ヒロインを通して描きたかった“得体の知れない恋の力”」 [mi-mollet]
『寝ても覚めても』原作者、「ヒロインを通して描きたかった“得体の知れない恋の力”」 [mi-mollet]
2018年09月04日(火) 14時10分配信
9月1日公開の映画『寝ても覚めても』は、恋愛の“甘さ”と“獰猛さ”の両方を感じさせる恋愛映画。「映画を見て、後半の展開に“ええっ!”となりました(笑)。自分で書いたくせに“なんてことを書いてしまったんだろう…”って」。原作者の柴崎友香さんがそんな風に語る物語は、恋の力に突き動かされるヒロインが最後に起こす、神をも恐れぬ行動に驚かされます。彼女の姿を通じて柴崎さんが描きたかったことは、いったいどんなことなのでしょうか?
作家 柴崎友香
1973年、大阪生まれ。’99年、短編「レッド、イエロー、オレンジ、オレンジ、ブルー」が 文藝別冊に掲載されデビュー。2000年に初の単行本『きょうのできごと』刊行(2003年に行定勲監督により映画化)。’10年に『寝ても覚めても』で第32回野間文芸新人賞受賞。'14年『春の庭』で芥川賞を受賞。小説作品に『ビリジアン』『パノララ』『わたしがいなかった街で』『週末カミング』『千の扉』、エッセイに『よう知らんけど日記』『よそ見津々』など著書多数。最新刊は『公園へ行かないか? 火曜日に』。
恋の呪いに囚われて、世界が歪み、感覚がグラつく
『寝ても覚めても』のヒロインは20代の朝子。突然姿を消した“運命の人”=麦(ばく)と、彼と同じ顔を持つ別の男性=亮平の間で揺れています。想像するだにドラマティックかつモヤモヤしそうな展開ですが、小説の中で丁寧に積み重ねられてゆくのは、朝子のなんということのない日常です。
でも柴崎友香さんの描くそれは、“何の変哲もない日常”とはちょっと違うかもしれません。例えば、見上げたアーケードの半透明な屋根を歩く猫が次の瞬間にいなくなっていたり、近くの自動車工場が火事になって突然爆発音が響いたり――朝子とはほとんど関係がない、周辺で起きる小さなエピソードが、微妙な違和感とともにいくつもさしはさまれています。
「日常の中で“あれ、なんかちょっと変?”と思うことが起きても、たいていの人が反応せずにスルーしてしまいますよね。あと見慣れた風景の中で何か取り壊してるけど、ここって何があったっけ?と思うこともよくあります。人間って周りの物事を見ているようで見ていないし、客観的なようでいて思い込みで見ていることがほとんどなんです。自分の顔すらもそう。不意に撮られた写真を見て“自分ってこんな顔だった?”とビックリしたり。そういう、自分の世界が歪むような、感覚がぐらつくような瞬間を、どうしたら小説で書けるかなといつも考えています。それが、人生を動かすようなこともあるんじゃないかなと」
たとえば「麦(ばく)」と「亮平」。映画では東出昌大さんが一人二役で演じていますが、画がない小説では「似ていると言えば、まあまあ似てる」という描写もあるように、本当にソックリなのかどうかは定かではありません。
「でも朝子は麦への思いに囚われていて、ずっと彼の面影を追い求めているんです。だからそっくりに見えてしまうところがあるんでしょうね」
これこそ、映画化作品の濱口竜介監督が言うところのこの作品のキモ。「まるで呪いのような、恋の不思議な力」です。
でも柴崎友香さんの描くそれは、“何の変哲もない日常”とはちょっと違うかもしれません。例えば、見上げたアーケードの半透明な屋根を歩く猫が次の瞬間にいなくなっていたり、近くの自動車工場が火事になって突然爆発音が響いたり――朝子とはほとんど関係がない、周辺で起きる小さなエピソードが、微妙な違和感とともにいくつもさしはさまれています。
「日常の中で“あれ、なんかちょっと変?”と思うことが起きても、たいていの人が反応せずにスルーしてしまいますよね。あと見慣れた風景の中で何か取り壊してるけど、ここって何があったっけ?と思うこともよくあります。人間って周りの物事を見ているようで見ていないし、客観的なようでいて思い込みで見ていることがほとんどなんです。自分の顔すらもそう。不意に撮られた写真を見て“自分ってこんな顔だった?”とビックリしたり。そういう、自分の世界が歪むような、感覚がぐらつくような瞬間を、どうしたら小説で書けるかなといつも考えています。それが、人生を動かすようなこともあるんじゃないかなと」
たとえば「麦(ばく)」と「亮平」。映画では東出昌大さんが一人二役で演じていますが、画がない小説では「似ていると言えば、まあまあ似てる」という描写もあるように、本当にソックリなのかどうかは定かではありません。
「でも朝子は麦への思いに囚われていて、ずっと彼の面影を追い求めているんです。だからそっくりに見えてしまうところがあるんでしょうね」
これこそ、映画化作品の濱口竜介監督が言うところのこの作品のキモ。「まるで呪いのような、恋の不思議な力」です。
「周りにどう思われるか」を恐れず、心のままに行動を起こすヒロイン
「恋愛って、普段の自分では考えられないことをやらかす、やらかしてしまえる、貴重な機会だなと思うんです。何をするにも先回りで考えてしてしまう今の時代、自分の枠から大きく踏み外す行動ってなかなかできないですよね。そんな中でも恋愛には、周囲の人々や自分さえもビックリするようなことをさせてしまう、できてしまえる、得体のしれない力がある。そこに興味がありました」
朝子の最初の恋の相手は、生まれ故郷の大阪で運命的に出会った麦(ばく)。外の世界から来た浮世離れした麦は、朝子を別の世界に連れ出してくれるような存在です。他方、二度目の恋の相手である亮平は、麦を失った後に越した東京で出会い、やがて共に暮らし始める大阪出身の男性。朝子にとって現実味のない東京で、地に足がついた安心感を与えてくれる存在です。
夢と現実を象徴するような二人の男性の間で、朝子はまさに「ゆめうつつ」の状態で揺れています。ところが。ある出来事をきっかけに、朝子は驚くべき行動に出ることになります。
「物語の最後には、朝子が自分の気持ちを信じて行動する。それは最初から決めていました。その道を行けば周囲との軋轢は避けられないかもしれないけれど、それでも踏み出す瞬間を自分は書きたかったのかなと思います。女性って周囲を考えて諦めてしまいがちなところがありますが、それは別の見方をすれば、自分の決断を人のせいにしているのかもしれない。それゆえにあとで後悔したりいつまでも思いが残ってしまうことも。誰が決めたのでもなく自分の決断で、その結果起こることはすべて自分が引き受ける。彼女の行動には賛否両論があると思いますが、何かを決断するならば、これくらいの強さがあっていいと思うんですよね」
朝子の最初の恋の相手は、生まれ故郷の大阪で運命的に出会った麦(ばく)。外の世界から来た浮世離れした麦は、朝子を別の世界に連れ出してくれるような存在です。他方、二度目の恋の相手である亮平は、麦を失った後に越した東京で出会い、やがて共に暮らし始める大阪出身の男性。朝子にとって現実味のない東京で、地に足がついた安心感を与えてくれる存在です。
夢と現実を象徴するような二人の男性の間で、朝子はまさに「ゆめうつつ」の状態で揺れています。ところが。ある出来事をきっかけに、朝子は驚くべき行動に出ることになります。
「物語の最後には、朝子が自分の気持ちを信じて行動する。それは最初から決めていました。その道を行けば周囲との軋轢は避けられないかもしれないけれど、それでも踏み出す瞬間を自分は書きたかったのかなと思います。女性って周囲を考えて諦めてしまいがちなところがありますが、それは別の見方をすれば、自分の決断を人のせいにしているのかもしれない。それゆえにあとで後悔したりいつまでも思いが残ってしまうことも。誰が決めたのでもなく自分の決断で、その結果起こることはすべて自分が引き受ける。彼女の行動には賛否両論があると思いますが、何かを決断するならば、これくらいの強さがあっていいと思うんですよね」
自分が生きている世界が、「ゆめ」か「うつつ」かわからない
今回の映画化で、小説『寝ても覚めても』を改めて読み直したという柴崎さん。書いてから10年近くたっていますが、その当時よりも今の方が、この作品で描いたものがリアルに感じられたといいます。
「朝子は自分の仕事も持ち、ちゃんと生活を営んではいるけれど、周りの世界と自分がうまくかみ合っていないような感覚を生きている人です。そういう感覚は、今という時代を生きる多くの人が持ち合わせているものじゃないでしょうか。職場と家を往復するだけの毎日で、周りの世界ばかりがキラキラして見え、そこに自分がなじんでないような、そんな感覚。SNSの世界は特にそういうものがあるのかもしれません。きれいに加工した写真で、過去も現在も同じ平面に並んでいる世界にいると、誰かが作り上げたイメージを生きているのか、現実を生きているのか、わからなくなるようなところがありますよね」
例えばインスタグラムでは、国内の利用者の半数を30代以上が占めると言います。“ここではないどこか”“この人でないあの人”を思いながら生きる朝子の姿に、わずかながら自分を見出してしまうミモレ世代の女性も、もしかしたら少なくないのかもしれません。自分で選び、自分で決断する人生にするために――何よりも大事なのは、「自分の実感」を持つことだと柴崎さんは言います。
「加工した写真の真っ青な空を見慣れてしまうと、本物の空が青く感じられなかったり、物足りなく思えたりしますよね。でもその一方で、写真で見た美味しそうな料理を食べたり、息を飲む絶景の場所に行ってみたりして、“え?こんなもん?”と思うことも(笑)。今の時代って、“これが美味しい”“これが素敵”と提示されたものを、誰もが基準にしてしまいがちですよね。でも他の人がどう思ったかより、自分自身が、美味しい、楽しい、イマイチと思う、自分の実感を大事にしながら生きた方がずっといい。人生なんてこんなもんかなと思うことがあっても、他と比べて卑下することなんてありません。よくインスタントラーメンの袋に、具がいっぱい乗った豪勢な完成図が描かれていますよね。でも“これはイメージです”し、最初から実物とはかけ離れたものなんです。比べ過ぎてもいいことはないんですよね」
「朝子は自分の仕事も持ち、ちゃんと生活を営んではいるけれど、周りの世界と自分がうまくかみ合っていないような感覚を生きている人です。そういう感覚は、今という時代を生きる多くの人が持ち合わせているものじゃないでしょうか。職場と家を往復するだけの毎日で、周りの世界ばかりがキラキラして見え、そこに自分がなじんでないような、そんな感覚。SNSの世界は特にそういうものがあるのかもしれません。きれいに加工した写真で、過去も現在も同じ平面に並んでいる世界にいると、誰かが作り上げたイメージを生きているのか、現実を生きているのか、わからなくなるようなところがありますよね」
例えばインスタグラムでは、国内の利用者の半数を30代以上が占めると言います。“ここではないどこか”“この人でないあの人”を思いながら生きる朝子の姿に、わずかながら自分を見出してしまうミモレ世代の女性も、もしかしたら少なくないのかもしれません。自分で選び、自分で決断する人生にするために――何よりも大事なのは、「自分の実感」を持つことだと柴崎さんは言います。
「加工した写真の真っ青な空を見慣れてしまうと、本物の空が青く感じられなかったり、物足りなく思えたりしますよね。でもその一方で、写真で見た美味しそうな料理を食べたり、息を飲む絶景の場所に行ってみたりして、“え?こんなもん?”と思うことも(笑)。今の時代って、“これが美味しい”“これが素敵”と提示されたものを、誰もが基準にしてしまいがちですよね。でも他の人がどう思ったかより、自分自身が、美味しい、楽しい、イマイチと思う、自分の実感を大事にしながら生きた方がずっといい。人生なんてこんなもんかなと思うことがあっても、他と比べて卑下することなんてありません。よくインスタントラーメンの袋に、具がいっぱい乗った豪勢な完成図が描かれていますよね。でも“これはイメージです”し、最初から実物とはかけ離れたものなんです。比べ過ぎてもいいことはないんですよね」
著者PROFILE
柴崎 友香Tomoka Shibasaki
1973年、大阪生まれ。’99年、短編「レッド、イエロー、オレンジ、オレンジ、ブルー」が 文藝別冊に掲載されデビュー。2000年に初の単行本『きょうのできごと』刊行(2003年に行定勲監督により映画化)。’10年に『寝ても覚めても』で第32回野間文芸新人賞受賞。'14年『春の庭』で芥川賞を受賞。小説作品に『ビリジアン』『パノララ』『わたしがいなかった街で』『週末カミング』『千の扉』、エッセイに『よう知らんけど日記』『よそ見津々』など著書多数。最新刊は『公園へ行かないか? 火曜日に』。