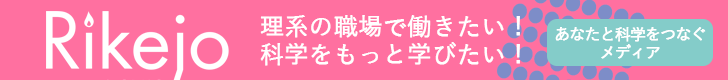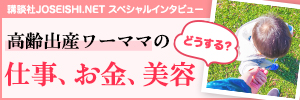- TOP
- > NEWS&TOPICS一覧
- > 考えを押し付けない、西加奈子の子育て論[家族のかたち] [FRaU]
考えを押し付けない、西加奈子の子育て論[家族のかたち] [FRaU]
2018年04月25日(水) 11時00分配信
最近ますます多様化している、家族のかたちとそこで生まれる悩みの数々。いくつになっても生きていく上で、いろんなときに、いろいろな場面で喜びも悲しみも、苦労も幸せも運んでくる存在。そんな「家族」を考えることで、30代のいまのいろいろを考える「なにか」になれば。
近著『i』では、血縁にたよらない家族のかたちを描いた。自身は、父の転勤でイラン、エジプトで幼少期を、20代後半まで大阪で過ごす。6年前に結婚、昨年母になったばかりの西加奈子さんに、いま彼女が抱く家族観を尋ねた。
近著『i』では、血縁にたよらない家族のかたちを描いた。自身は、父の転勤でイラン、エジプトで幼少期を、20代後半まで大阪で過ごす。6年前に結婚、昨年母になったばかりの西加奈子さんに、いま彼女が抱く家族観を尋ねた。
我が子に、スペシャルな気持ちを過剰に抱きたくない
育児と仕事の両立も、母業も始まったばかりで、手探りだ。試行錯誤の道程で、昨日わからなかった謎が、今日解けることもある。
たとえば、出産したとき、空恐ろしい感覚があった。
「子どもにとって、私と夫は家族の最小単位になる。それがとんでもなく怖いなと思ってしまって。私の感覚が、子どものすべての基準になると思うと、さらに怖い。いてもたってもいられず、友達に相談したら “あんたの感覚って、親に似てる?” って聞かれたんです。“あー、似てないわー” それでね、楽になれたんです。親子だからって、すべて一緒じゃないんだなって」
子どもは、今はまだ、母としては認識しているかわからないが、少なくとも “大切な人” という認識はあるようだ。大切な絆をもつ親子ではあるが、西さんは独特の距離感を抱く。
「私はおっぱいがあるだけ。子どもにとって、そのくらいの存在でいい。私もまた必要以上に愛さなくていいと思っています。自分の子どもだけ、自分の家族だけ幸せならいいという考えはいやなんです。我が子はスペシャルですが、過剰にスペシャルな接し方はしないでおこうとこころがけています。
もちろん愛しているけれど、だからといって愛を返してくれなくていい。母が悲しむからこういう選択をしないでおこうと思う人になってしまうかもしれない。それは違うし、そう思ってほしくないんです。我慢しないでほしい。ひとりの人間として尊重したいし、自由に生きてほしいです」
自身、両親からそのような距離感で育った。いつでも絶対的な味方だが、自分の考えを押し付けることは一切なかった。だから、どんな人とつきあおうがなにも言わず、交友関係に口出しをされなかったし、勉強をしていい大学に行けとも、いい会社に入れとも言われたことがないのだ。そこには、ひとりの自立した人間として、尊重する視点が通底している。
たとえば、出産したとき、空恐ろしい感覚があった。
「子どもにとって、私と夫は家族の最小単位になる。それがとんでもなく怖いなと思ってしまって。私の感覚が、子どものすべての基準になると思うと、さらに怖い。いてもたってもいられず、友達に相談したら “あんたの感覚って、親に似てる?” って聞かれたんです。“あー、似てないわー” それでね、楽になれたんです。親子だからって、すべて一緒じゃないんだなって」
子どもは、今はまだ、母としては認識しているかわからないが、少なくとも “大切な人” という認識はあるようだ。大切な絆をもつ親子ではあるが、西さんは独特の距離感を抱く。
「私はおっぱいがあるだけ。子どもにとって、そのくらいの存在でいい。私もまた必要以上に愛さなくていいと思っています。自分の子どもだけ、自分の家族だけ幸せならいいという考えはいやなんです。我が子はスペシャルですが、過剰にスペシャルな接し方はしないでおこうとこころがけています。
もちろん愛しているけれど、だからといって愛を返してくれなくていい。母が悲しむからこういう選択をしないでおこうと思う人になってしまうかもしれない。それは違うし、そう思ってほしくないんです。我慢しないでほしい。ひとりの人間として尊重したいし、自由に生きてほしいです」
自身、両親からそのような距離感で育った。いつでも絶対的な味方だが、自分の考えを押し付けることは一切なかった。だから、どんな人とつきあおうがなにも言わず、交友関係に口出しをされなかったし、勉強をしていい大学に行けとも、いい会社に入れとも言われたことがないのだ。そこには、ひとりの自立した人間として、尊重する視点が通底している。
だが、西さん自身は、「本来、利己的で独占欲が強い」と自己分析する。
「仲のいい友達とスクラムを組んで、その子達とだけ遊んで、その子達にしかわからない会話をしがち。自分が子どもを産んだら “私のもの” って思いかねない。だからこそ、ひとりの人間として尊重しよう。ちゃんとした距離感を持とうと思ったのです」
お母さんはこう思うけど、あなたはどう思う?と聞く。「ふつうはこうするものだよ」「みんなはこれができるよ」は絶対に言うまいと誓っている。
「主語をweにしない。weやみんなを主語にすると、“自分も皆と同じでないといけない” という思考になります。みんなに笑われることが怖くなってしまう。だから、weはやめておこうと」
小説との向き合い方で、正直に生きて笑われるのなら、喜んで笑われることを引き受けると語った西さんらしい。裏返せば、みんなに笑われることを恐れて、自分に嘘をつくような人間になってほしくないということでもある。
トークショーでも、つとめて「私はこう考えている」と伝えるよう気をつけている。それが世界のすべて、と思ってほしくないからだ。
「私の言葉で救われたと言われたら、それは嬉しいけれど、世の中にはなんぼでも意見がある。世の中に書籍がこれだけあるというのも、それだけ多様な意見があるという証。それに言葉は、ときに呪いになることもありますから」
子育ても同じだ。「私はこう思うけれどお父さんはこう思わないかもしれない。世の中にはいろんな考え方があるのだと知り、それらを参考に自分の頭で考えられる人間になってほしい」と、西さんはまっすぐの瞳で語る。
「仲のいい友達とスクラムを組んで、その子達とだけ遊んで、その子達にしかわからない会話をしがち。自分が子どもを産んだら “私のもの” って思いかねない。だからこそ、ひとりの人間として尊重しよう。ちゃんとした距離感を持とうと思ったのです」
お母さんはこう思うけど、あなたはどう思う?と聞く。「ふつうはこうするものだよ」「みんなはこれができるよ」は絶対に言うまいと誓っている。
「主語をweにしない。weやみんなを主語にすると、“自分も皆と同じでないといけない” という思考になります。みんなに笑われることが怖くなってしまう。だから、weはやめておこうと」
小説との向き合い方で、正直に生きて笑われるのなら、喜んで笑われることを引き受けると語った西さんらしい。裏返せば、みんなに笑われることを恐れて、自分に嘘をつくような人間になってほしくないということでもある。
トークショーでも、つとめて「私はこう考えている」と伝えるよう気をつけている。それが世界のすべて、と思ってほしくないからだ。
「私の言葉で救われたと言われたら、それは嬉しいけれど、世の中にはなんぼでも意見がある。世の中に書籍がこれだけあるというのも、それだけ多様な意見があるという証。それに言葉は、ときに呪いになることもありますから」
子育ても同じだ。「私はこう思うけれどお父さんはこう思わないかもしれない。世の中にはいろんな考え方があるのだと知り、それらを参考に自分の頭で考えられる人間になってほしい」と、西さんはまっすぐの瞳で語る。
サム・クックを聴いて思わず涙 自由を奪われるのがいちばんつらい
夫は「我が子をすこやかに育てるチームメイト」だ。チームの意識は新婚時代からあったが、出産をしてより強くなったとのこと。
しかし、日中はそのチームメイトもいない。出産して半年。実感したのは「自由への渇望」だ。
「私は自由を奪われることが一番つらいんだなって、わかりました。産後一ヵ月は外に出られないのがしんどかった。それはもう泣きたくなるくらいつらかったですね。マジで、犯罪だけは犯さないようにしようって心に誓いましたもん(笑)」
乳児を抱えて密室で悪戦苦闘。大好きなお酒を飲みに行くことはもちろん、友達に会うことさえままならない。「いつか、きっと変化は訪れる」と、黒人の人種差別を歌ったサム・クックの『A Change Is Gonna Come』を夜中に聴いたときは、思わず涙が溢れた。
「自由を奪われるとはどれほど辛いことかと。自由は全員にあるべき。ひとりだけ自由がないというのはつらいですね」
もちろん公民権運動と密室の子育てのつらさを並列で語れるはずもないが、西さんが感じた苦痛は、彼女だけの問題ではない。核家族化、経済至上主義による長時間労働とも無縁ではなく、乳児を抱えた多くの家庭が共感する社会問題ともいえそうだ。
外出できない新生児時代は過ぎ、今はベビーシッターの手を借り、仕事との両立をはかっている。まだまだ思うように時間をつくれないが、それでも小さな自由はいくらか手に入った。とくに同業者や不規則な仕事を持つママ友との会話は支えになっている。
「仕事時間の確保とか、自分の睡眠とかどうしてる?と、先輩ママたちに会ったらすぐきいちゃいます。みんなそれぞれ工夫してがんばっているから、励みや参考になりますね。ネットやテレビはほとんど見ません。ネットは、自分から探しに行かない限り情報は入ってこない。だから振り回されることもありません」
夜の授乳や成長の具合など、悩んでもネットではなく経験者たちに聞いて、あとは自分の判断で。しなやかに、という言葉通り、「こうでなければ」という既成概念を捨て、状況に合わせてトライ&エラーを続けている。
しかし、日中はそのチームメイトもいない。出産して半年。実感したのは「自由への渇望」だ。
「私は自由を奪われることが一番つらいんだなって、わかりました。産後一ヵ月は外に出られないのがしんどかった。それはもう泣きたくなるくらいつらかったですね。マジで、犯罪だけは犯さないようにしようって心に誓いましたもん(笑)」
乳児を抱えて密室で悪戦苦闘。大好きなお酒を飲みに行くことはもちろん、友達に会うことさえままならない。「いつか、きっと変化は訪れる」と、黒人の人種差別を歌ったサム・クックの『A Change Is Gonna Come』を夜中に聴いたときは、思わず涙が溢れた。
「自由を奪われるとはどれほど辛いことかと。自由は全員にあるべき。ひとりだけ自由がないというのはつらいですね」
もちろん公民権運動と密室の子育てのつらさを並列で語れるはずもないが、西さんが感じた苦痛は、彼女だけの問題ではない。核家族化、経済至上主義による長時間労働とも無縁ではなく、乳児を抱えた多くの家庭が共感する社会問題ともいえそうだ。
外出できない新生児時代は過ぎ、今はベビーシッターの手を借り、仕事との両立をはかっている。まだまだ思うように時間をつくれないが、それでも小さな自由はいくらか手に入った。とくに同業者や不規則な仕事を持つママ友との会話は支えになっている。
「仕事時間の確保とか、自分の睡眠とかどうしてる?と、先輩ママたちに会ったらすぐきいちゃいます。みんなそれぞれ工夫してがんばっているから、励みや参考になりますね。ネットやテレビはほとんど見ません。ネットは、自分から探しに行かない限り情報は入ってこない。だから振り回されることもありません」
夜の授乳や成長の具合など、悩んでもネットではなく経験者たちに聞いて、あとは自分の判断で。しなやかに、という言葉通り、「こうでなければ」という既成概念を捨て、状況に合わせてトライ&エラーを続けている。
本は、自由を教えてくれる
子どもにとって、自由を知る最初の一歩は読書であると考えている。それは自分の経験から悟った。
「小学校5年のとき、カイロから帰国してすごくしんどかったんです。カイロでは男の子とも喧嘩したり、自己主張も強くて調子に乗ってたんです。そのノリで大阪に帰ったら浮いてしまって、自分の居場所がなくて。調子に乗っていたので、あそこでガーンとやられてよかったんですけれどね、そのとき救いになったのが文通と本でした」
カイロの日本人学校で知り合い、日本に帰国した女の子と文通を始めた。
「彼女は、エジプトの話をすると、みんなが、わ〜聞かせて聞かせてと寄ってくる、と。人気者だったんです。そういう世界もあるんだ、今いる世界だけが全てじゃないんだなとわかり、糧になりました。彼女は今も大切な親友です」
小説も、その場にいながら、違う世界にいける。物理的にも精神的にも不自由でも、本を読むと、いくらでも自由になれる。西さんは、小説の世界にどんどんはまっていった。
高校1年。本屋でアメリカの黒人女性作家、トニ・モリスンの小説『青い眼がほしい』と出会う。これが、彼女が小説の力を信じる決定的な作品となった。
「言葉ってこんな力があるんだ、と衝撃を受けました。そのころ音楽も映画もいろいろ見たり聴いたりしていたけれど、モリスンの衝撃はすごかった。高1って自意識全開のころじゃないですか。小説では、黒人の女の子が、白人のベビードールをもらって“かわいいでしょ?”と言われる。そこでモリスンは“かわいい”ってなに?と問いかけるんです。そして、自分とはぜんぜん違う“かわいい”の解釈があることを知る。
私は、当時セーラー服の制服が着たくてその高校に入ったのですが、誰がセーラー服を“かわいい”と決めたのか。あるいは、ブルマを履きたいと思っている子が本当にいるのか。モリスンの小説から、自分が疑問にも思っていなかった“なぜ”を突きつけられました。とても大きな出会いでした」
「小学校5年のとき、カイロから帰国してすごくしんどかったんです。カイロでは男の子とも喧嘩したり、自己主張も強くて調子に乗ってたんです。そのノリで大阪に帰ったら浮いてしまって、自分の居場所がなくて。調子に乗っていたので、あそこでガーンとやられてよかったんですけれどね、そのとき救いになったのが文通と本でした」
カイロの日本人学校で知り合い、日本に帰国した女の子と文通を始めた。
「彼女は、エジプトの話をすると、みんなが、わ〜聞かせて聞かせてと寄ってくる、と。人気者だったんです。そういう世界もあるんだ、今いる世界だけが全てじゃないんだなとわかり、糧になりました。彼女は今も大切な親友です」
小説も、その場にいながら、違う世界にいける。物理的にも精神的にも不自由でも、本を読むと、いくらでも自由になれる。西さんは、小説の世界にどんどんはまっていった。
高校1年。本屋でアメリカの黒人女性作家、トニ・モリスンの小説『青い眼がほしい』と出会う。これが、彼女が小説の力を信じる決定的な作品となった。
「言葉ってこんな力があるんだ、と衝撃を受けました。そのころ音楽も映画もいろいろ見たり聴いたりしていたけれど、モリスンの衝撃はすごかった。高1って自意識全開のころじゃないですか。小説では、黒人の女の子が、白人のベビードールをもらって“かわいいでしょ?”と言われる。そこでモリスンは“かわいい”ってなに?と問いかけるんです。そして、自分とはぜんぜん違う“かわいい”の解釈があることを知る。
私は、当時セーラー服の制服が着たくてその高校に入ったのですが、誰がセーラー服を“かわいい”と決めたのか。あるいは、ブルマを履きたいと思っている子が本当にいるのか。モリスンの小説から、自分が疑問にも思っていなかった“なぜ”を突きつけられました。とても大きな出会いでした」
小説は多様な自由と価値観を教えてくれる。
「これを読むとつらいことになるぞ。見たくないものを見ることになりそうだぞとわかっていても読みたいのです。今は書く側になりましたが、変わりません。世界中のつらいことをできれば知りたくないし、知らなければ楽に生きられるし、考えずにすみます。パレスチナの、シリアの、ロヒンギャの子どもが毎日死んでいるということを知らないほうが楽だけど、でも知らないといけない。絶対見たくないけれど見ないといけない、書かないといけないことがあると思っています」
’14年に上梓した『舞台』について、自ら解説したものに次の一説がある。
『これまでの小説を、憧れの世界を自由に書いたものと、書かないといけない、という思いで苦しんで書いたものに分けるとすると、これはそのどちらにも足をかけている気がします。』(「西加奈子による自作解説」)
つまり、触れなければ楽だが、苦しくとも書かねばならないという小説が、彼女の作品にはあるということだ。それは、読むとつらくなりそうだとわかっていても読むことで、新しい自由を知ったあの頃の自分のような人間に向けて、書いているのかもしれない。もっと大きな自分の世界、自由を手に入れるために。
「これを読むとつらいことになるぞ。見たくないものを見ることになりそうだぞとわかっていても読みたいのです。今は書く側になりましたが、変わりません。世界中のつらいことをできれば知りたくないし、知らなければ楽に生きられるし、考えずにすみます。パレスチナの、シリアの、ロヒンギャの子どもが毎日死んでいるということを知らないほうが楽だけど、でも知らないといけない。絶対見たくないけれど見ないといけない、書かないといけないことがあると思っています」
’14年に上梓した『舞台』について、自ら解説したものに次の一説がある。
『これまでの小説を、憧れの世界を自由に書いたものと、書かないといけない、という思いで苦しんで書いたものに分けるとすると、これはそのどちらにも足をかけている気がします。』(「西加奈子による自作解説」)
つまり、触れなければ楽だが、苦しくとも書かねばならないという小説が、彼女の作品にはあるということだ。それは、読むとつらくなりそうだとわかっていても読むことで、新しい自由を知ったあの頃の自分のような人間に向けて、書いているのかもしれない。もっと大きな自分の世界、自由を手に入れるために。
柔軟に、しなやかに
最後に、西さんは、子どもには読書の他に、英語を習わせたいなあとつぶやいた。
「日本でしか生きられない人間になってほしくないので。英語ができたらさらにいろんな自由、世界を知ることができますものね?」
その反面、本当に英語でなければいけないのか?という思いもなくはない。
「ノーベル平和賞の最年少受賞者、マララさんは英語でスピーチをしていましたね。あれはパキスタン語でいいんじゃないかな?ってふと思いました。母国語は美しい。みんながみんな、英語を喋らなくてもいいんじゃないかなあって」
自分が良かれと思っている価値観が本当に良いのか、自問自答する母の真摯な姿がそこにあった。
リングの真ん中に立ち、書くことで、人はひとりではないと力強く言い続ける小説家の、プライベートの小さな迷いがちらりと見えた瞬間。親業はまだ始まったばかり。答えはひとつではない。自由に、柔軟に。小説『i』でも描いた愛を信じる力を糧に、しなやかな価値観で、彼女なりの家族のかたちが築かれてゆくのだろう。
さて、母となった彼女の作品が変わるのか変わらないのか。書くことで、「あなたは自由なんだと全力で伝えたい」と語る彼女の次作を、私たちは静かに待ちたい。
「日本でしか生きられない人間になってほしくないので。英語ができたらさらにいろんな自由、世界を知ることができますものね?」
その反面、本当に英語でなければいけないのか?という思いもなくはない。
「ノーベル平和賞の最年少受賞者、マララさんは英語でスピーチをしていましたね。あれはパキスタン語でいいんじゃないかな?ってふと思いました。母国語は美しい。みんながみんな、英語を喋らなくてもいいんじゃないかなあって」
自分が良かれと思っている価値観が本当に良いのか、自問自答する母の真摯な姿がそこにあった。
リングの真ん中に立ち、書くことで、人はひとりではないと力強く言い続ける小説家の、プライベートの小さな迷いがちらりと見えた瞬間。親業はまだ始まったばかり。答えはひとつではない。自由に、柔軟に。小説『i』でも描いた愛を信じる力を糧に、しなやかな価値観で、彼女なりの家族のかたちが築かれてゆくのだろう。
さて、母となった彼女の作品が変わるのか変わらないのか。書くことで、「あなたは自由なんだと全力で伝えたい」と語る彼女の次作を、私たちは静かに待ちたい。
PROFILE
西加奈子 Nishi Kanako
1977年、テヘラン生まれ。小1~5年までカイロ、以降は大阪で育つ。2004年、『あおい』で小説家としてデビュー。’07年に『通天閣』で織田作之助賞、’13年に『ふくわらい』で河合隼雄物語賞、’15年に『サラバ!』で直木賞を受賞。近著に『i』がある。’12年、編集者と結婚。’17年7月出産。ベビーシッターの手を借りつつ、仕事と育児を両立中。
1977年、テヘラン生まれ。小1~5年までカイロ、以降は大阪で育つ。2004年、『あおい』で小説家としてデビュー。’07年に『通天閣』で織田作之助賞、’13年に『ふくわらい』で河合隼雄物語賞、’15年に『サラバ!』で直木賞を受賞。近著に『i』がある。’12年、編集者と結婚。’17年7月出産。ベビーシッターの手を借りつつ、仕事と育児を両立中。
※FRaU2018年3月号より一部抜粋
●情報は、FRaU2018年3月号発売時点のものです。
●情報は、FRaU2018年3月号発売時点のものです。