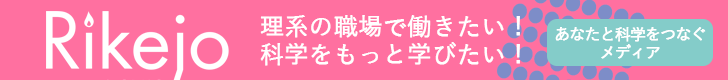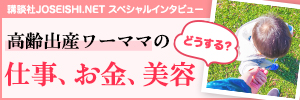- TOP
- > NEWS&TOPICS一覧
- > 黒柳徹子ロングインタビュー「38歳で迎えた大きな転機の話」 [FRaU]
黒柳徹子ロングインタビュー「38歳で迎えた大きな転機の話」 [FRaU]
2017年07月01日(土) 11時00分配信
自分の居場所はどこにあるのか。今の仕事は自分に本当に合っているのだろうか。いっそ、ここではないどこかへ旅立って、自分を試してみたい――。黒柳徹子インタビュー全文公開。
自分を必要としてくれて 仕事があるということは、 なんとありがたいことか
ニューヨークで充実した毎日を過ごす徹子さんのもとに、あるとき、「ニュースショーの司会をしませんか?」という依頼が日本から舞い込んだ。
まだまだ学びたいことはたくさんあった。でも、ブロードウェイでは、能力はあっても仕事にありつけない人をたくさん見てきた。
「それで、自分を必要としてくれて、仕事があるということは、なんてありがたいんだろうと気づいて」
留学から1年、徹子さんは帰国を決意する。当時は、ニュースショーやワイドショーの司会は主婦の経験のある人がほとんどだった。
「ですから私は、当時のプロデューサーに『私は独身ですし、白のブラウスに紺のタイトスカートでなるたけ無難に、というわけには、いきませんけれど』と申し上げたんです。そうしたら、『いいですよ、時代は変わっています』と言っていただいたので、お引き受けすることにしました」
ところで、徹子さんが、毎年舞台に立っていることを知らない人もいるかもしれない。徹子さんはこの「13時ショー」の司会を約3年務め、番組はニュースショーからトークショーへと移行し、それが「徹子の部屋」となった。
「徹子の部屋」が始まって間もなく、ある出来事によって、徹子さんは、女優の仕事は舞台だけにしようと決心したのだ。
「若尾文子さんと一緒にテレビドラマで芸者さんの役をやったとき、ほろ酔い加減の芸者さんの芝居が、かなり真に迫っていたんでしょうね(苦笑)。撮影の合間に、小道具さんが私のところにやってきて、『本当は飲んでるんでしょ?』って言うんです。私、ビックリしちゃって! 普段でもお酒が飲めないのに、うまくやると、本当に飲んでいると思い込んじゃうのね。じゃあ、テレビで悪女の役を演じてしまったら、視聴者は、『徹子の部屋』を観ながら、『あの人、本当は悪女なのに、こんなに真面目に人の話なんか聞いちゃって』みたいに思うってことじゃない? それはよくないなぁ、と。
あとは、テレビだと、40代の女優に来る役は、お母さんとかばっかりで、お母さんでもおばあさんでもない、ヘンなお姉さんの役とか、全然ないの(笑)。そんなことがいろいろ重なって、じゃあもう、演じるのは舞台だけにしよう、と」
そうこうしているうちに、かつて「一丁目一番地」というラジオドラマで夫婦役を演じた高橋昌也さんが、今はなき銀座セゾン劇場の芸術監督に就任され「出てみませんか?」と誘われた。それが、30年続く徹子さんのライフワーク「海外コメディ・シリーズ」の始まりだった。日本では、あまり女性が主役のコメディは見かけないが、海外にはたくさんある。
「世の中って、つらいこと、哀しいことがどうしても多いけれど、せめてお芝居を観た後ぐらいは、『わー、面白かった』って、楽しんでもらって帰っていただきたい。だから、私は喜劇にこだわっているのです」
かつて、永六輔さんはこんなことを言っていた。
「生まれてきて、黒柳徹子の芝居を見ないで死んだらソンだ。そのくらい、黒柳徹子の芝居は面白い」
今年の演目は、「レティスとラベッジ」。'89年、「海外コメディ・シリーズ」の第1弾で、山岡久乃さんと共演した、徹子さんにとって非常に思い出深い作品の、再再演となる。
まだまだ学びたいことはたくさんあった。でも、ブロードウェイでは、能力はあっても仕事にありつけない人をたくさん見てきた。
「それで、自分を必要としてくれて、仕事があるということは、なんてありがたいんだろうと気づいて」
留学から1年、徹子さんは帰国を決意する。当時は、ニュースショーやワイドショーの司会は主婦の経験のある人がほとんどだった。
「ですから私は、当時のプロデューサーに『私は独身ですし、白のブラウスに紺のタイトスカートでなるたけ無難に、というわけには、いきませんけれど』と申し上げたんです。そうしたら、『いいですよ、時代は変わっています』と言っていただいたので、お引き受けすることにしました」
ところで、徹子さんが、毎年舞台に立っていることを知らない人もいるかもしれない。徹子さんはこの「13時ショー」の司会を約3年務め、番組はニュースショーからトークショーへと移行し、それが「徹子の部屋」となった。
「徹子の部屋」が始まって間もなく、ある出来事によって、徹子さんは、女優の仕事は舞台だけにしようと決心したのだ。
「若尾文子さんと一緒にテレビドラマで芸者さんの役をやったとき、ほろ酔い加減の芸者さんの芝居が、かなり真に迫っていたんでしょうね(苦笑)。撮影の合間に、小道具さんが私のところにやってきて、『本当は飲んでるんでしょ?』って言うんです。私、ビックリしちゃって! 普段でもお酒が飲めないのに、うまくやると、本当に飲んでいると思い込んじゃうのね。じゃあ、テレビで悪女の役を演じてしまったら、視聴者は、『徹子の部屋』を観ながら、『あの人、本当は悪女なのに、こんなに真面目に人の話なんか聞いちゃって』みたいに思うってことじゃない? それはよくないなぁ、と。
あとは、テレビだと、40代の女優に来る役は、お母さんとかばっかりで、お母さんでもおばあさんでもない、ヘンなお姉さんの役とか、全然ないの(笑)。そんなことがいろいろ重なって、じゃあもう、演じるのは舞台だけにしよう、と」
そうこうしているうちに、かつて「一丁目一番地」というラジオドラマで夫婦役を演じた高橋昌也さんが、今はなき銀座セゾン劇場の芸術監督に就任され「出てみませんか?」と誘われた。それが、30年続く徹子さんのライフワーク「海外コメディ・シリーズ」の始まりだった。日本では、あまり女性が主役のコメディは見かけないが、海外にはたくさんある。
「世の中って、つらいこと、哀しいことがどうしても多いけれど、せめてお芝居を観た後ぐらいは、『わー、面白かった』って、楽しんでもらって帰っていただきたい。だから、私は喜劇にこだわっているのです」
かつて、永六輔さんはこんなことを言っていた。
「生まれてきて、黒柳徹子の芝居を見ないで死んだらソンだ。そのくらい、黒柳徹子の芝居は面白い」
今年の演目は、「レティスとラベッジ」。'89年、「海外コメディ・シリーズ」の第1弾で、山岡久乃さんと共演した、徹子さんにとって非常に思い出深い作品の、再再演となる。
誰にとっても、 猛然と一人になって考える時間は必要
ニューヨークでの留学生活を振り返って、「誰にとっても、猛然と、一人になって考える時期は必要なのかもしれない」と徹子さんは言う。
「一人暮らしに少し自信を持ち、自分で洋服を2着半つくり、セーターを1枚つくり、芝居を観にきただけじゃないんだぞ、と思ったので、芝居はあんまり観ないで、その代わりいろんな人生を見て、私は、帰ってきたのです」
徹子さんは、ニューヨークで大勢の俳優と出会った。ヘンリー・フォンダ、キャサリン・ヘプバーン、ブロードウェイで活躍する、徹子さんが大尊敬する俳優、ゼロ・モステル……。いい俳優に逢ってわかったのは、どの人にも人間的魅力があふれているということだった。
そんなふうな、やさしくて、愛情があふれるようにあるって人を何人か見たのが、私のこの一年のいちばんの収穫でした。俳優というのはね、人が悪くて、イヤな人、といわれても、芸さえありゃいいってもんじゃないってこと、よくわかりました。
徹子さんがニューヨークで見つめた様々な人たちの人生――。それらは、確実に女優としての身になった。「人間的でありたい」。それから「創造的な仕事は、命をかけてやらなきゃつまらない」。この二つが、徹子さんがニューヨーク留学で学んだ、もっとも大切なことだった。
「一人暮らしに少し自信を持ち、自分で洋服を2着半つくり、セーターを1枚つくり、芝居を観にきただけじゃないんだぞ、と思ったので、芝居はあんまり観ないで、その代わりいろんな人生を見て、私は、帰ってきたのです」
徹子さんは、ニューヨークで大勢の俳優と出会った。ヘンリー・フォンダ、キャサリン・ヘプバーン、ブロードウェイで活躍する、徹子さんが大尊敬する俳優、ゼロ・モステル……。いい俳優に逢ってわかったのは、どの人にも人間的魅力があふれているということだった。
そんなふうな、やさしくて、愛情があふれるようにあるって人を何人か見たのが、私のこの一年のいちばんの収穫でした。俳優というのはね、人が悪くて、イヤな人、といわれても、芸さえありゃいいってもんじゃないってこと、よくわかりました。
人がよいばっかりで、いい俳優になれなかった人も、たくさんいるってことはわかるんだけれど、最終的に残るのは、大事なのは、その人の人間性なのね。芸は人なりってこと、昔からあったけれど、今度、それがはっきりわかったのでした。(『チャックより愛をこめて』より)
徹子さんがニューヨークで見つめた様々な人たちの人生――。それらは、確実に女優としての身になった。「人間的でありたい」。それから「創造的な仕事は、命をかけてやらなきゃつまらない」。この二つが、徹子さんがニューヨーク留学で学んだ、もっとも大切なことだった。
この世は生きるのも難しいけれど、 死ぬのも難しい。人生って、 そんなもんじゃないかと思うのです
一年のニューヨーク生活の中で、数え切れないほどの収穫があった。たくさんの人と出会い、女優としての想像力を強化し、一人暮らしの大変さと仕事のあるありがたみが身にしみた。
そんな未来への希望や日常生活の充実感、人々への感謝を実感するとともに、徹子さんはある種の絶望感のようなものを抱え込む。「それは、アメリカで逢った、たくさんのおばあさんのせいかもしれない」と徹子さんは話す。
「私はよく、ニューヨークでセントラルパークをぶらぶらして、そこにいる人をじーっと眺めていました。よく旦那様に先立たれたおばあさんに話しかけられて、聞くと、『夫をなくして5年も経つのに、誰かに慰めてほしくて仕方がない』って言うんです。アメリカの男性って、奥さんに対して、しょっちゅう『子猫ちゃん』だの『シュガー』だの呼びかけて、ハグしたり、キスしたりするから、そういう相手を失うと、寂しくて仕方がなくなる。
そんな寂しそうなおばあさんに出会うたびに思ったんです。〝人間は、どうしたって歳を取っていく。ならば、どう上手く歳をとって、上手く死ねるか〞。この世は生きるのも難しいけれど、死ぬのも難しい。そうか、人生って、そういうものなんだな、って」
昔、親友の向田邦子さんから「禍福は糾(あざな)える縄の如し」(〝幸福と不幸は、縒り合わせた縄のように交互にやってくる〞の意)ということわざを聞いたとき、「私は、不幸はイヤ。幸福だけがいい」と徹子さんは言った。「そういうわけにはいかないのよ」と向田さんは苦笑いした。
でも、ニューヨークで猛然と人生について考え、生まれて初めて市井の人の人生をまっすぐ見つめたとき、〝上手に生きることと上手に死ぬことは、誰にとっても難しい。易々と生きて、易々と死ねる人生などどこにもない〞というひとつの真理に気づく。生きることと死ぬことの難しさは、お金持ちでも貧乏人でも、美人でもそうでない人でも、若い人でも年老いた人でも、誰にとっても平等なのだと。
生きていけば、この先も、まだまだたくさんの困難が待っている。しかも、人は誰もが〝死〞に向かって生きているのだ。その〝気づき〞は、ずっと好奇心いっぱいに生きてきた徹子さんの心に、絶望という名の大きな影を落とした。でも、生と死が隣り合わせにあるように、絶望と希望もまた、いつも隣り合わせだ。
俳優にとって幸いなのは、 どんな経験も、すべて 演じる上で役に立つということ
「ただ、俳優にとって幸いなのは、どんな経験も、すべて演じる上で役に立つということ。もちろんそれは、つらく厳しいことでもあるのだけれど」
徹子さんの数ある著書の中でも、〝絶望感〞に深く言及しているのは、『チャックより愛をこめて』だけである。このニューヨーク留学で、あらゆる人たちの人生に思いをめぐらし、ひとつの真理に気づいたことで、徹子さんは、無限の想像力を手に入れた。
そうして、世の中にはつらいことや悲しいことが多すぎるからこそ、せめて舞台を観ている間は、そんなことを忘れてほしい、と願うのだ。
『チャックより愛をこめて』は、徹子さんが '71年の9月から '72年の9月までの1年間を過ごしたアメリカから、日本に向けて送ったいろいろな文章がまとめられたものだ。その最終章には、こんなユーモラスな文章がある。
かつて、若かりし徹子さんが俳優の小沢昭一さんに向かって、「私は100歳まで生きるんだ!」と言ったことがある。すると小沢さんは、「そんなに生きたら、寂しいよ」と徹子さんを諭したという。「だって、同じ時代を過ごした人がみんな死んでしまって、〝あの頃こうだったわね〞なんて話しても、誰も覚えている人がいないんだよ」
想像したら悲しくなって、20代の徹子さんはワーワー声をあげて泣いた。
昨年、徹子さんの大好きだった人たちとの思い出を綴った『トットひとり』を書いたあと、徹子さんはこんなことを言っていた。
「この本を書いたことで、死ぬことがそんなにつらくないと感じるようになりました。だって、死ぬということは、森繁さん、沢村貞子さん、小沢昭一さん、渥美清さん、向田さん……。あんなに素晴らしくて個性的な人たちが、みんな経験したことなんですから」
かつて共演して、徹子さんがその芝居に大いに感銘を受けた先輩の俳優たちの多くは、もうこの世にはいない。まだまだいろんな役を演じたかっただろうし、演じてほしかったと徹子さんは思う。だからこそ、毎年舞台に立てることに、心から感謝し、舞台に立つ前には必ずその人たちのことを思い出し、祈るのだ。「今日も私のことを見守っていてください」と――。
徹子さんの数ある著書の中でも、〝絶望感〞に深く言及しているのは、『チャックより愛をこめて』だけである。このニューヨーク留学で、あらゆる人たちの人生に思いをめぐらし、ひとつの真理に気づいたことで、徹子さんは、無限の想像力を手に入れた。
そうして、世の中にはつらいことや悲しいことが多すぎるからこそ、せめて舞台を観ている間は、そんなことを忘れてほしい、と願うのだ。
『チャックより愛をこめて』は、徹子さんが '71年の9月から '72年の9月までの1年間を過ごしたアメリカから、日本に向けて送ったいろいろな文章がまとめられたものだ。その最終章には、こんなユーモラスな文章がある。
そうそう、私がいない間、妊娠七ヶ月であるという噂が、週刊誌に出ました。こればかりは、どうして出たかナントモカントモ、私には、わからないんだけれど、まあどうしてもっていえば、私の着ていた服が、このブァッとした妊娠ルックみたいなのだったからかしら。
かつて、若かりし徹子さんが俳優の小沢昭一さんに向かって、「私は100歳まで生きるんだ!」と言ったことがある。すると小沢さんは、「そんなに生きたら、寂しいよ」と徹子さんを諭したという。「だって、同じ時代を過ごした人がみんな死んでしまって、〝あの頃こうだったわね〞なんて話しても、誰も覚えている人がいないんだよ」
想像したら悲しくなって、20代の徹子さんはワーワー声をあげて泣いた。
昨年、徹子さんの大好きだった人たちとの思い出を綴った『トットひとり』を書いたあと、徹子さんはこんなことを言っていた。
「この本を書いたことで、死ぬことがそんなにつらくないと感じるようになりました。だって、死ぬということは、森繁さん、沢村貞子さん、小沢昭一さん、渥美清さん、向田さん……。あんなに素晴らしくて個性的な人たちが、みんな経験したことなんですから」
かつて共演して、徹子さんがその芝居に大いに感銘を受けた先輩の俳優たちの多くは、もうこの世にはいない。まだまだいろんな役を演じたかっただろうし、演じてほしかったと徹子さんは思う。だからこそ、毎年舞台に立てることに、心から感謝し、舞台に立つ前には必ずその人たちのことを思い出し、祈るのだ。「今日も私のことを見守っていてください」と――。
PROFILE
黒柳徹子 TESTUKO KUROYANAGI
東京都乃木坂生まれ。ライフワークである「黒柳徹子海外コメディ・シリーズ」が1989年にスタート。その第一回作品は、ロンドンを舞台に、おしゃべりガイドと堅物職員がトークバトルを繰り広げる「レティスとラベッジ」だった。ユーモアとペーソスにあふれた傑作が、2016年秋、初演から27年ぶり、再演からは16年ぶりにリニューアル上演された。
東京都乃木坂生まれ。ライフワークである「黒柳徹子海外コメディ・シリーズ」が1989年にスタート。その第一回作品は、ロンドンを舞台に、おしゃべりガイドと堅物職員がトークバトルを繰り広げる「レティスとラベッジ」だった。ユーモアとペーソスにあふれた傑作が、2016年秋、初演から27年ぶり、再演からは16年ぶりにリニューアル上演された。