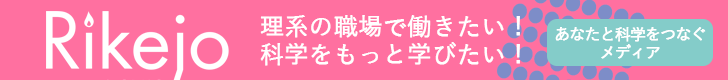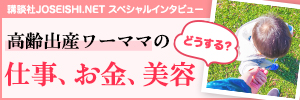- TOP
- > NEWS&TOPICS一覧
- > 伝説の作家・白洲正子 当時のファッション誌も注目する彼女のライフスタイルとは? [おとなスタイル]
伝説の作家・白洲正子 当時のファッション誌も注目する彼女のライフスタイルとは? [おとなスタイル]
2016年07月23日(土) 09時00分配信
一期一会とは、私流に解釈すれば、結局
自分自身と出会うことである──『縁あって』より
まず最初に得たのは、なんと健康で、「私はふだん病気がちなので、旅行に出る前は、不安であった。実際に、紀州を回る間は疲れがひどく、いつまでつづくか危ぶまれたが、四、五番を終えるころから、見ちがえるように丈夫になった」(『巡礼の旅 西国三十三ヵ所』より)と、書くほどだった。
47歳のときに出版したエッセイ集『韋駄天(いだてん)夫人』は、青山二郎に“韋駄天お正”と綽名(あだな)されたことに由来するタイトルで、好奇心の赴くままに「かけずりまわる」生来の行動派であった正子だが、同時に、若いころから病床に伏せることも多く、これは思いがけないご利益だった。おそらく更年期を乗りこえるのにも、絶好の機会だったのだろう。
開発の波に押され、失われていく古来の風景は、そこここにあった。痛々しい様子を目の当たりにしながら、正子はひたすら歩いた。
「最近は観光ブームにのって、スキー場その他の施設がふえて行く。町にとってはうれしい繁栄ぶりだろうが、このままで行くと、天の橋立も、今に伝説と化すかもしれない。そういうおそれは多分にある」(『巡礼の旅 西国三十三ヵ所』より)と、時折不安げにつぶやきながら。
“巡礼の時代”に執筆された本を読み進めると、白洲正子の感性、審美眼というものが、歩くほどに明快になり、輪郭を見せていくように感じる。太古の記憶に繋がる自然への共感という、白洲正子の美意識に行き渡る感覚が、スケール感を増していく。
「そこには悠久の時間だけがあり、見物人も神主も、私自身さえ消え失せ、遠い過去から照らす光の中に、身をゆだねているような心地であった」(『かくれ里』より)
こうした日本の原風景との交感を、何度も経験している。それはおそらく、骨董を求め、能面を求め、また、経営する「こうげい」のために染織作家のもとを訪ねる時代から繰り返してきた、無意識の感じ方だったろう。この資質が、旅をすることで研ぎすまされ、たとえば焼物ならば、器と風土が離れがたく見えるようになる。
「ちょうど秋の暮のことで、山は紅葉に染まり、その間を陶土そのままの真白な道が重なり合い、その二つを切り放しては考えられなくなった。壺を眺めていると、山里の秋が目の前に浮かんで来る、というより、私は既にその中に居る」(『近江山河抄』より)といったふうに。そしてついには、「私は美術品が、夢にもわかるとは思っていないが、自分の好きなものだけは、はっきりしている。それを知るために何十年もかかったといっていい」(『縁あって』より)の域までになるのだ。
また、「巡礼の意味は、旅するところにある。一つの札所から、次の札所への『道中』にある」(『巡礼の旅 西国三十三ヵ所』より)と記すように、点を訪ねるのではなく、点から点への移動を重んじるようになる。かけずりまわる若き韋駄天ではなく、ゆっくりと坂道や石段、杣道(そまみち)を歩く、大人の歩調。興味を引くものがあれば、立ち寄りもする。
彼女はそれを道草と呼んでいて、「私の人生は道草ばかり」と冗談めかして語りもするが、道草で得た縁が次の執筆につながっていく。歩けばこその収穫である。
50代の正子は、いや、晩年に近づくまで、美術・文芸系や婦人誌に主に執筆していた。そんなカルチャー系の白洲正子を、ファッション誌が取り上げるようになったのは、バブル崩壊の時期に重なっている。
『フィガロジャポン』の1993年4月号。特集のタイトルは、「白洲正子の美の世界」。綴じ込み保存版だった。
それまで日本のファッション誌は、ライフスタイルのお手本を、海外にばかり求めてきた。ジャクリーン・オナシス、キャサリン・ヘプバーン、もしくはジェーン・バーキン。自由で勇気あるハンサムウーマンたちだ。しかし、最強のアイコンが日本に存在することを、ファッション誌は発見したのだ。時に正子、83歳。
手入れの行き届いた古民家で暮らす姿。日々愛用している骨董の身近に置きたくなる趣味のよさ。
常滑(とこなめ)の瓶に投げ入れたやまぼうしは、フラワーアレンジメントにはない野性味がある。室内に据えられた英国製のアームチェアの重厚な存在感。すべてに、住まう人の趣味と体温が行き渡っている。
バブル景気が崩壊し、日本は恒久的に続くと思い込んでいた成長の夢から醒めはじめていた。海外旅行やグルメ、高級ブランド品など、自己投資という名の消費に現(うつつ)を抜かしていた日本の女性たち(つまりは私たちの世代)は、海外に身を置く経験を経て、自国の文化を語れない我が身に気がつく。これまで眼中になかった日本のことを、もっと知りたいと思い始めたのだ。白洲正子は、日本の“ほんもの”を知る賢者として脚光を浴びることとになる。
自分自身と出会うことである──『縁あって』より
まず最初に得たのは、なんと健康で、「私はふだん病気がちなので、旅行に出る前は、不安であった。実際に、紀州を回る間は疲れがひどく、いつまでつづくか危ぶまれたが、四、五番を終えるころから、見ちがえるように丈夫になった」(『巡礼の旅 西国三十三ヵ所』より)と、書くほどだった。
47歳のときに出版したエッセイ集『韋駄天(いだてん)夫人』は、青山二郎に“韋駄天お正”と綽名(あだな)されたことに由来するタイトルで、好奇心の赴くままに「かけずりまわる」生来の行動派であった正子だが、同時に、若いころから病床に伏せることも多く、これは思いがけないご利益だった。おそらく更年期を乗りこえるのにも、絶好の機会だったのだろう。
開発の波に押され、失われていく古来の風景は、そこここにあった。痛々しい様子を目の当たりにしながら、正子はひたすら歩いた。
「最近は観光ブームにのって、スキー場その他の施設がふえて行く。町にとってはうれしい繁栄ぶりだろうが、このままで行くと、天の橋立も、今に伝説と化すかもしれない。そういうおそれは多分にある」(『巡礼の旅 西国三十三ヵ所』より)と、時折不安げにつぶやきながら。
“巡礼の時代”に執筆された本を読み進めると、白洲正子の感性、審美眼というものが、歩くほどに明快になり、輪郭を見せていくように感じる。太古の記憶に繋がる自然への共感という、白洲正子の美意識に行き渡る感覚が、スケール感を増していく。
「そこには悠久の時間だけがあり、見物人も神主も、私自身さえ消え失せ、遠い過去から照らす光の中に、身をゆだねているような心地であった」(『かくれ里』より)
こうした日本の原風景との交感を、何度も経験している。それはおそらく、骨董を求め、能面を求め、また、経営する「こうげい」のために染織作家のもとを訪ねる時代から繰り返してきた、無意識の感じ方だったろう。この資質が、旅をすることで研ぎすまされ、たとえば焼物ならば、器と風土が離れがたく見えるようになる。
「ちょうど秋の暮のことで、山は紅葉に染まり、その間を陶土そのままの真白な道が重なり合い、その二つを切り放しては考えられなくなった。壺を眺めていると、山里の秋が目の前に浮かんで来る、というより、私は既にその中に居る」(『近江山河抄』より)といったふうに。そしてついには、「私は美術品が、夢にもわかるとは思っていないが、自分の好きなものだけは、はっきりしている。それを知るために何十年もかかったといっていい」(『縁あって』より)の域までになるのだ。
また、「巡礼の意味は、旅するところにある。一つの札所から、次の札所への『道中』にある」(『巡礼の旅 西国三十三ヵ所』より)と記すように、点を訪ねるのではなく、点から点への移動を重んじるようになる。かけずりまわる若き韋駄天ではなく、ゆっくりと坂道や石段、杣道(そまみち)を歩く、大人の歩調。興味を引くものがあれば、立ち寄りもする。
彼女はそれを道草と呼んでいて、「私の人生は道草ばかり」と冗談めかして語りもするが、道草で得た縁が次の執筆につながっていく。歩けばこその収穫である。
50代の正子は、いや、晩年に近づくまで、美術・文芸系や婦人誌に主に執筆していた。そんなカルチャー系の白洲正子を、ファッション誌が取り上げるようになったのは、バブル崩壊の時期に重なっている。
『フィガロジャポン』の1993年4月号。特集のタイトルは、「白洲正子の美の世界」。綴じ込み保存版だった。
それまで日本のファッション誌は、ライフスタイルのお手本を、海外にばかり求めてきた。ジャクリーン・オナシス、キャサリン・ヘプバーン、もしくはジェーン・バーキン。自由で勇気あるハンサムウーマンたちだ。しかし、最強のアイコンが日本に存在することを、ファッション誌は発見したのだ。時に正子、83歳。
手入れの行き届いた古民家で暮らす姿。日々愛用している骨董の身近に置きたくなる趣味のよさ。
常滑(とこなめ)の瓶に投げ入れたやまぼうしは、フラワーアレンジメントにはない野性味がある。室内に据えられた英国製のアームチェアの重厚な存在感。すべてに、住まう人の趣味と体温が行き渡っている。
バブル景気が崩壊し、日本は恒久的に続くと思い込んでいた成長の夢から醒めはじめていた。海外旅行やグルメ、高級ブランド品など、自己投資という名の消費に現(うつつ)を抜かしていた日本の女性たち(つまりは私たちの世代)は、海外に身を置く経験を経て、自国の文化を語れない我が身に気がつく。これまで眼中になかった日本のことを、もっと知りたいと思い始めたのだ。白洲正子は、日本の“ほんもの”を知る賢者として脚光を浴びることとになる。
「武相荘」とは、武蔵と相模の境にあるこの地にちなんで、無愛想とかけて白洲次郎が名付けたのだそう。東京郊外の鶴川村にあった養蚕農家を買い取り、小石川水道町から移住した白洲夫妻。それから55年間暮らしつづけ、終の住み処に。
周囲には珍しい里山が残され、今もなお、当時の静かな空気の中で、ふたりの暮らしを体感することができる。
<文/田中敦子さん プロフィール>
1961年東京生まれ。工芸、きもの、日本文化を中心に、執筆、編集、プロデュースなどを行う。『もののみごと江戸の粋を継ぐ職人たちの、確かな手わざと名デザイン。』( 講談社)、『更紗』(誠文堂新光社)他、編著書多数。
おとなスタイルVol.3 2016 春号より
(撮影/浜村達也)
<文/田中敦子さん プロフィール>
1961年東京生まれ。工芸、きもの、日本文化を中心に、執筆、編集、プロデュースなどを行う。『もののみごと江戸の粋を継ぐ職人たちの、確かな手わざと名デザイン。』( 講談社)、『更紗』(誠文堂新光社)他、編著書多数。
おとなスタイルVol.3 2016 春号より
(撮影/浜村達也)